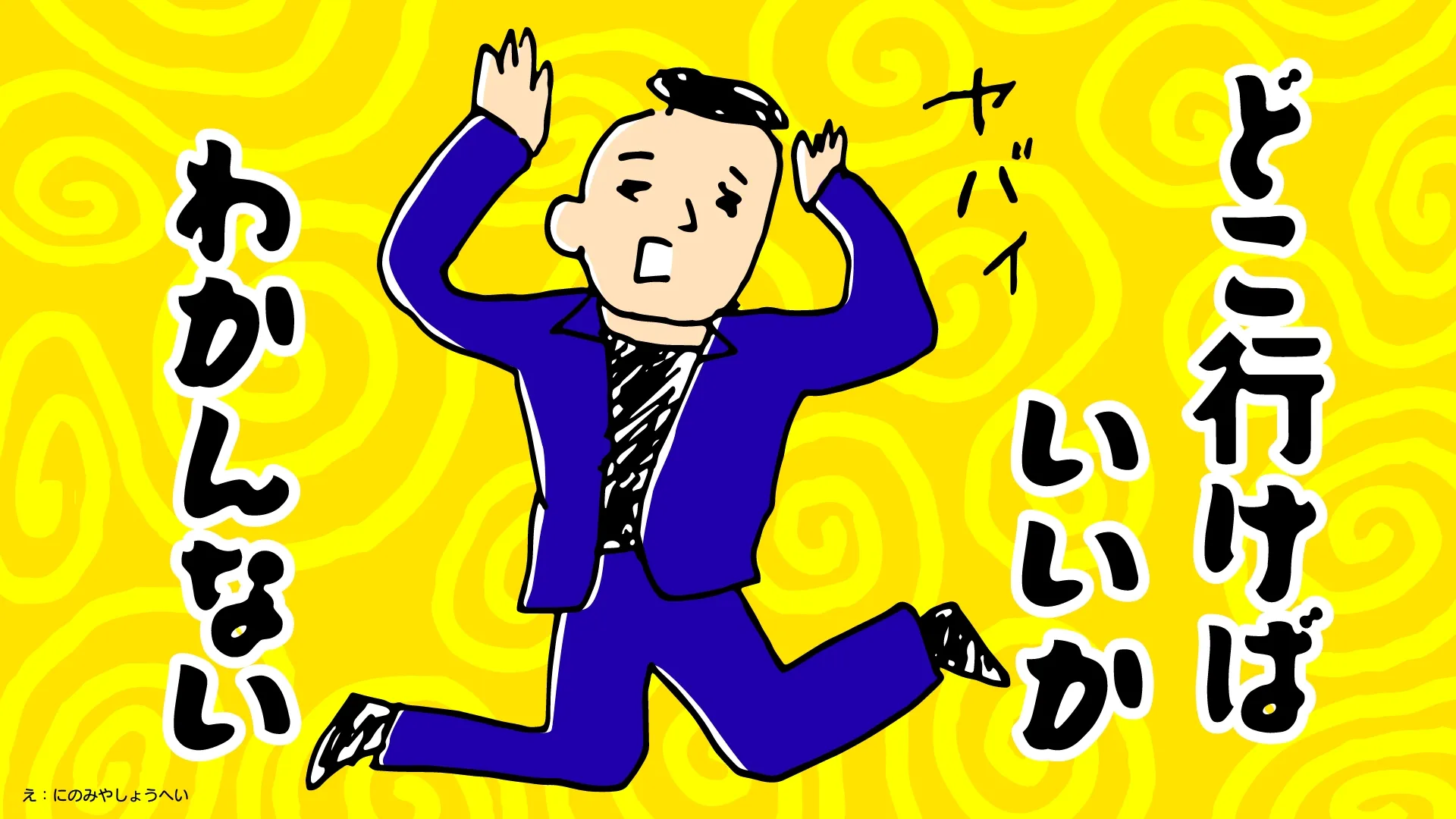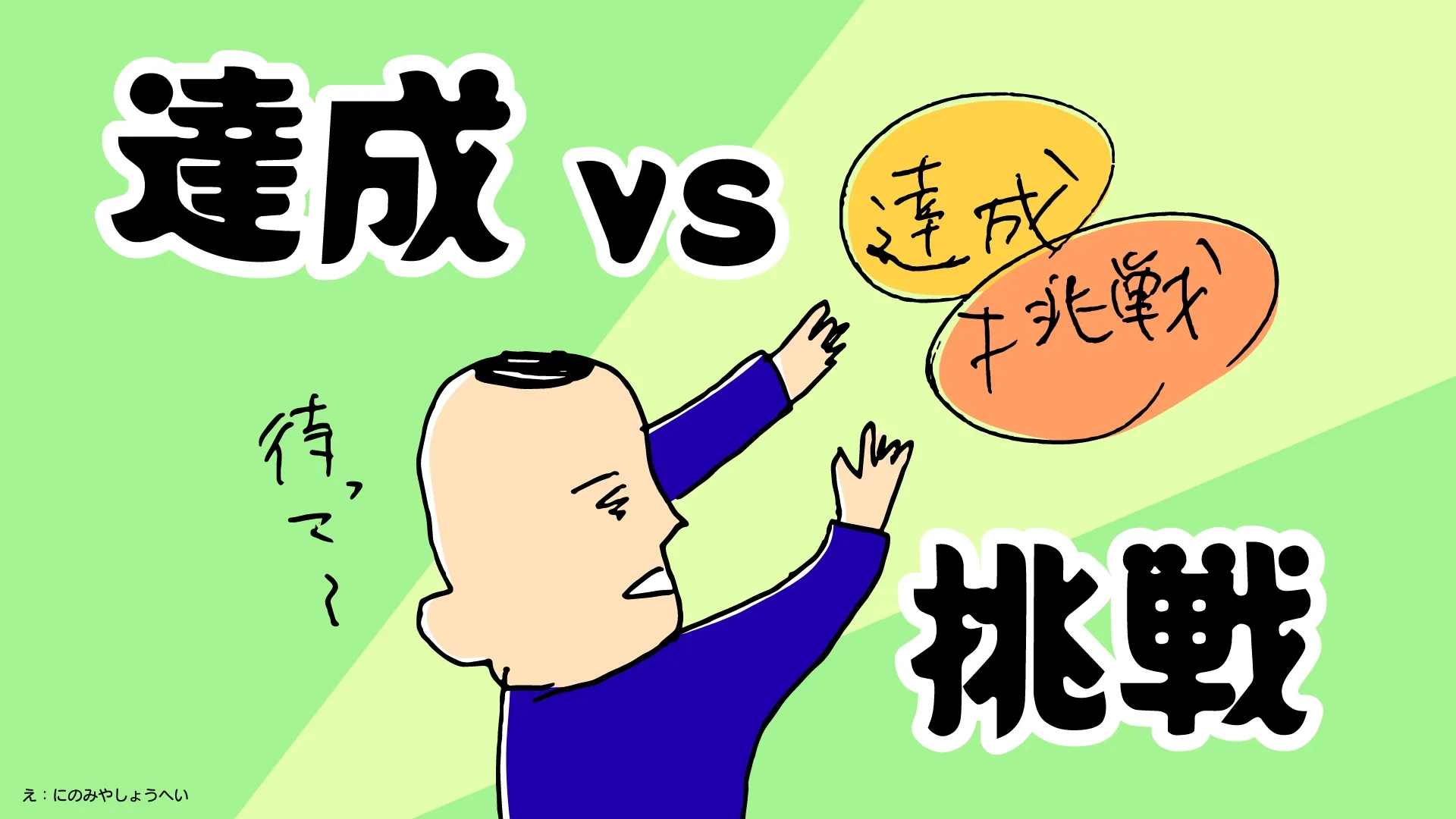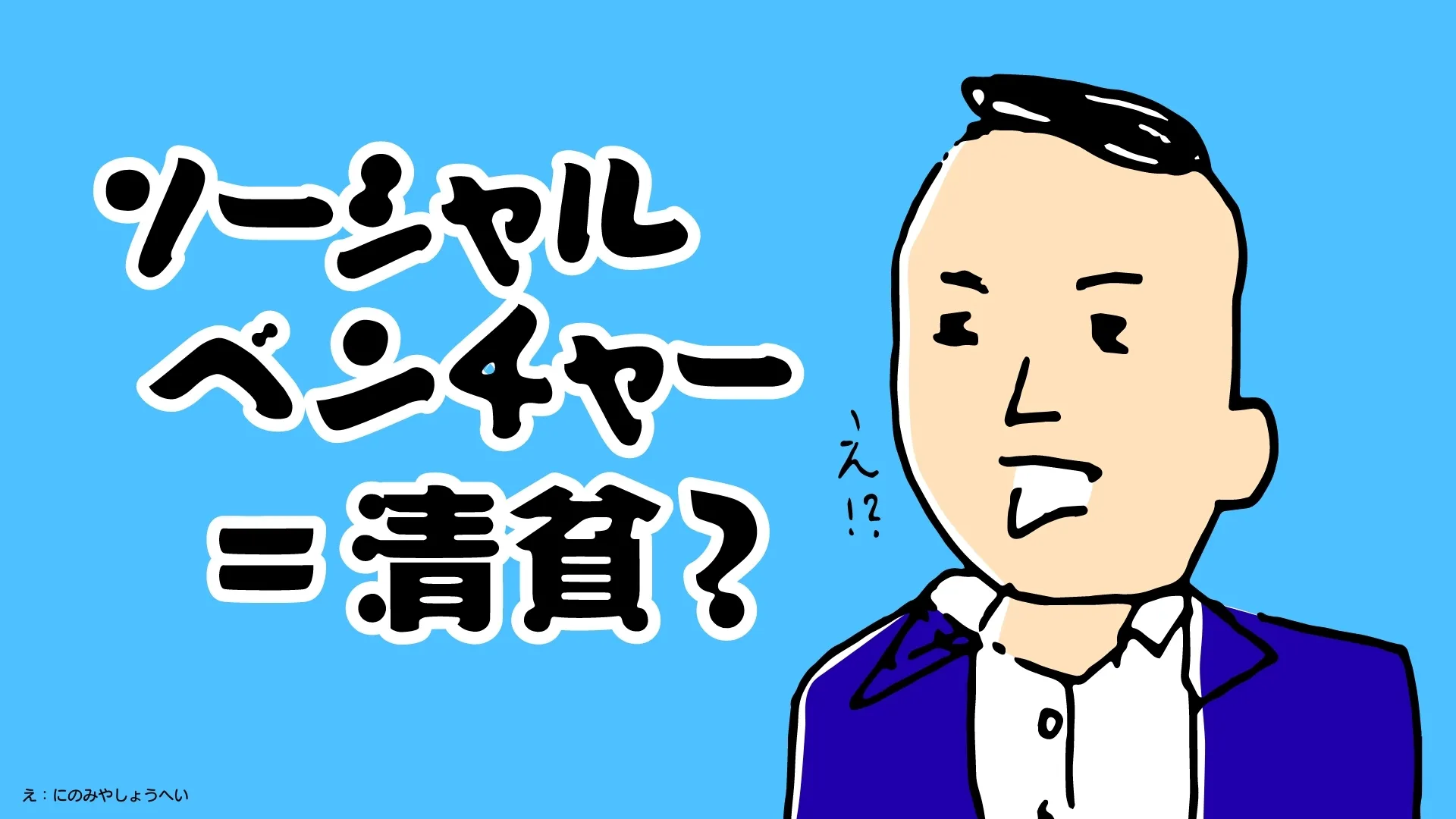【前編】行政と連携し困っている人を助ける「誰でもスマホ」創設秘話!
「行政と連携するためには最初どこに行けばいいのかわからなかった」
今回のテーマは「アーラリンクのサービスのお話」
行政と連携をしながらサービスを展開している「誰でもスマホ」
どのように行政との連携ができたのかのお話しました。
- 目次
- 早朝のルーチンと仕事のスタイル
- 生活リズムの工夫
- 行政との連携のはじまり
- 行政との最初の接点
- 解決策を求めて、全国行脚
- 公平性の壁を超える方法
- 厚生労働省へのアプローチ
- 自治体との試験導入
- 厚生労働省への正式な提案
- 全国展開への道
- まとめ:根気が結んだ行政との連携
早朝のルーチンと仕事のスタイル
おはようございます。最近、朝型の生活にシフトしているんです。もともと朝5時半に会社に行ってたんですが、今はさらに前倒しして、3時起きの4時半出社になりました。まるでパン屋さんのような時間帯ですよね(笑)。
普通の出勤時間は9時半なんですが、夜遅くまで残業するよりも、朝早く集まって仕事をする文化を作りたくて、8時からミーティングを入れるようにしています。でも、8時スタートだと頭が働かないので、それに備えてさらに早く起きる、という流れになりました。
会社まではタクシーで行って、帰りは歩いています。歩くと1時間くらいかかるんですが、いい運動になるので問題なし。でも、朝歩くのはちょっとキツいので、そこは割り切ってタクシーを使っています。
生活リズムの工夫
3時に起きるとなると、寝る時間も必然的に早くなります。なので、夜8時には寝るようにしています。うちの3歳の息子より早いんですよ(笑)。息子は9時に寝かせるんですが、なかなか寝ないので、ベッドに行っても9時半くらいまで起きてることが多いですね。
仕事が終わるのは大体5時半。そこから1時間歩いて帰って、6時半には家に到着。ご飯を食べて、お風呂に入って、犬の散歩をして…という感じで、寝るまでの時間をフル活用しています。犬の散歩は30分くらいしますが、この2時間の間にいろんなことを凝縮してやっている感じですね。
行政との連携のはじまり
今回のテーマは、僕たちの事業「誰でもスマホ」と行政の連携について。いつの間にか行政とつながっているように見えるかもしれませんが、実はかなり試行錯誤してきました。
元々は「WEBマーケ」を5年間やっていたんですが、ふと「もっと困っている人がいるんじゃないか?」と思ったんです。携帯を持てない人がWEBで申し込むのって、おかしくないですか? だって、そもそもネットがないと申し込めないんですよ。じゃあ、WEBがない人と出会える場所はどこか?と考えた時に、行政が浮かびました。ハローワークや生活保護の窓口には、携帯がなくて困っている人がいるはずだ、と
行政との最初の接点
まず、豊島区役所に行ってみました。すると、すぐに問題発生。実は生活保護を扱っているのは「福祉事務所」で、区役所とは場所が違うんです。そんなことも知らなかったので、「どこ行けばいいんですか?」って感じでしたね(笑)。
福祉事務所を見つけて、窓口の職員さんに「携帯がないことで困っている人って、どれくらいいるんですか?」と聞いてみたんです。そしたら、「結構いますよ」という反応。でも、「じゃあ、僕たちのサービスを紹介してもらえますか?」と聞いたら、「それはできません」と。理由は「行政は特定の民間企業を紹介できない」から。公平性の問題なんですよね。例えば、行政の工事を発注する時に入札が必要なのと同じで、1社だけを特別に紹介するのはダメなんです。いや、それはそうなんだけど、どうしたらいいんだ…って悩みましたね。
解決策を求めて、全国行脚
それでも諦めずに、東京23区すべての福祉事務所を回りました。さらに、埼玉や神奈川の自治体にも行き、ケースワーカーさんや就労支援員さんと話をしました。すると、中には「本当に困っている人がいるのは分かるし、何かできることはないか」と考えてくれる職員さんも出てきたんです。
例えば、ある職員さんは「公には紹介できないけど、アイコンタクトで伝えますね」と言ってくれました(笑)。どういうことかというと、僕が窓口に行くと、職員さんが黙って特定の人をじっと見てるんです。そこで僕が察して、「携帯がなくて困ってますか?」と声をかけると、「はい、困ってます」と。そのまま役所の外に出て、公園で契約をする、みたいなこともありました。完全にグレーゾーンですけど、本当に必要な人に届けるために、そういう工夫をしてくれる人もいたんですよね。
公平性の壁を超える方法
こういうやり方では広がらない。どうすれば公平性を担保しつつ、行政と連携できるのか? そこで思いついたのが「リスト化」でした。
つまり、僕たちの会社だけを紹介するのがダメなら、携帯会社の一覧を作ればいい。困っている人が契約できる会社をリスト化して、その中に僕たちの「アーラリンク」も入れてもらう。そうすれば、行政としても特定の企業を推奨するわけじゃなく、選択肢を提供する形になるんです。
でも、このリストを作って配るのは僕たちじゃなくて、厚生労働省がやるべきこと。だから、次の課題は「厚生労働省にどうやって話を持っていくか」でした。もちろん、厚労省に知り合いなんていません。どうやってつながればいいのか、ここからまた新たなチャレンジが始まるんです。
厚生労働省へのアプローチ
厚生労働省に知り合いがいるわけでもなく、どうやってこの問題を伝えればいいのか…と考えました。そもそも、厚労省の担当者とつながるにはどうすればいいのか? そこから試行錯誤が始まりました。
まず、行政に関するイベントやセミナーに参加してみました。そういう場には、自治体の職員や関係者が集まるので、何かしらのつながりができるかもしれないと考えたんです。実際に参加してみると、厚労省の人と直接話せる機会は少なかったですが、自治体の職員さんたちと知り合いになれました。
その中で、「うちの自治体で試験的にやってみてもいいかもしれない」と言ってくれる人が現れました。これが大きな一歩でした。自治体単位で導入事例を作り、それを積み重ねることで、厚生労働省に対して「すでにこういう事例があり、効果が出ている」という形で話を持っていけるんじゃないかと思ったんです。
自治体との試験導入
実際に、いくつかの自治体で「困窮者向けの携帯電話提供プログラム」を試験的に導入してもらいました。役所の窓口で「携帯がなくて困っている人がいたら、このリストを渡してください」とお願いし、僕たちのアーラリンクもその中に入れてもらう形にしました。
この方法なら、行政が特定の企業を紹介するわけではなく、選択肢の一つとして情報提供するだけなので、公平性の問題はクリアできます。こうして少しずつ行政の理解を得て、協力してもらえる自治体が増えていきました。
すると、ある自治体の職員さんが「この仕組みを厚生労働省に報告してみよう」と提案してくれたんです。ここでようやく、厚労省へのルートが見えてきました。
厚生労働省への正式な提案
厚労省にアプローチするために、自治体での成功事例をまとめた資料を作成しました。どの自治体でどのように運用されているのか、実際に携帯を手にした人がどのように変わったのか、数字とともに具体的なデータを用意しました。
そして、ある自治体の紹介で、厚労省の担当者とミーティングする機会を得ました。そこで、「困窮者支援の一環として携帯電話を提供することの重要性」を説明し、「全国的に導入するには厚労省がリストを作成し、各自治体に配布するのが最適ではないか?」と提案しました。
厚労省の担当者もこの問題の重要性は理解してくれましたが、やはりすぐに全国展開とはいきません。でも、「まずは一部の自治体でモデルケースを作って、それをもとに全国展開を検討する」という流れには持っていけました。
全国展開への道
厚労省とのミーティング後、さらにいくつかの自治体がこの取り組みに興味を示し、導入を決めました。結果として、行政と連携する形で、困窮者が携帯電話を持てるようになる仕組みが少しずつ整ってきたんです。
今では、厚労省の公式リストに「困窮者向けの携帯電話サービス」が掲載され、全国の自治体で使われるようになりました。ここに至るまで、相当な時間と労力がかかりましたが、諦めずに動き続けたことで、行政との連携が実現したんです。
まとめ:根気が結んだ行政との連携
この行政連携のプロセスを振り返ると、最初はまったくの手探りでした。でも、実際に現場に行き、職員さんと話し、小さな事例を積み重ねることで、大きな流れを作ることができました。
一見すると「行政との連携は難しい」と思われがちですが、根気強くアプローチし続ければ、必ず道は開けます。僕たちのようなソーシャルベンチャーが社会課題を解決していくためには、こうした地道な努力が欠かせないと改めて実感しました。
次回の放送では、さらに具体的な事例や、今後の展望について話していきます。お楽しみに!