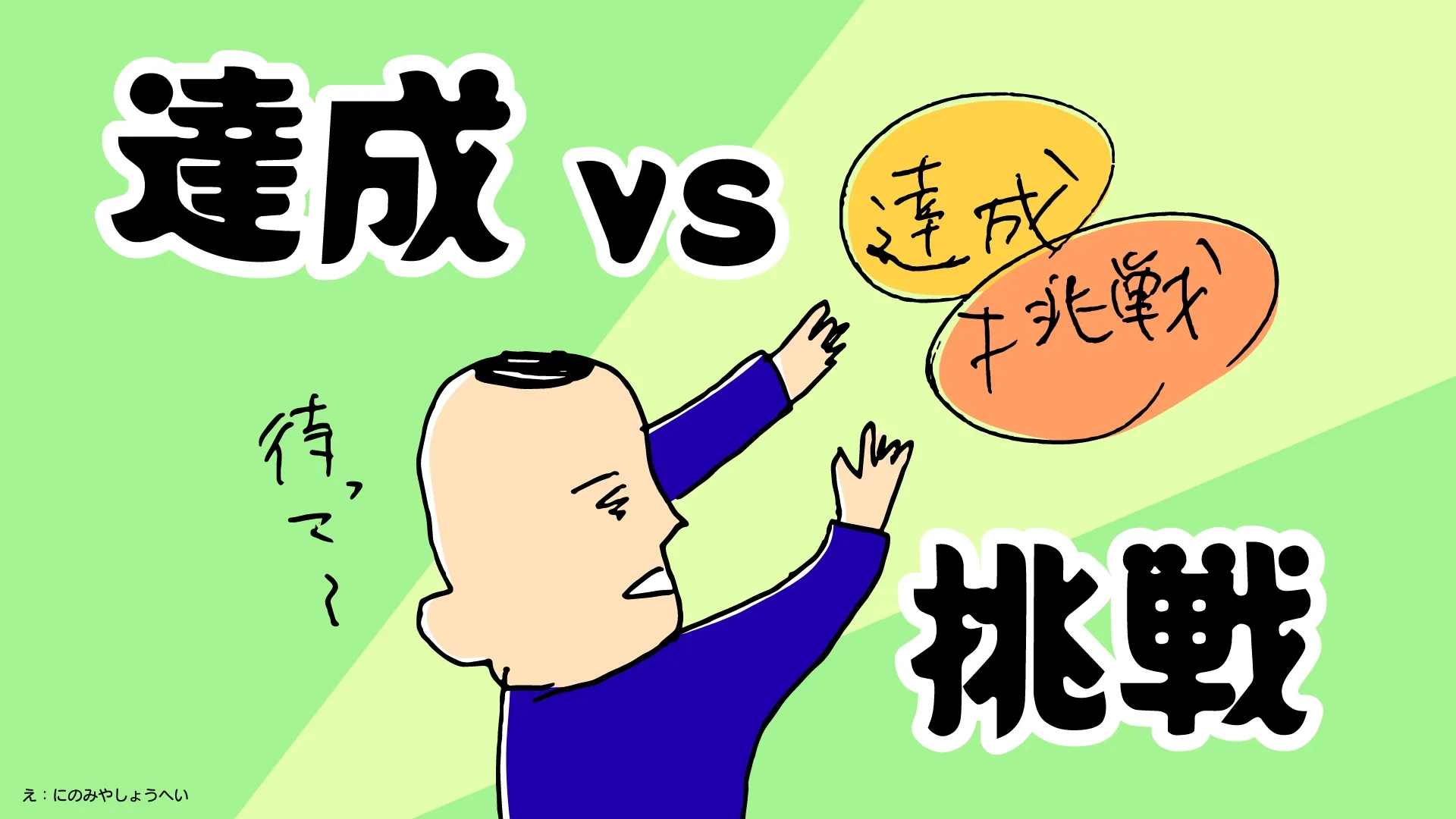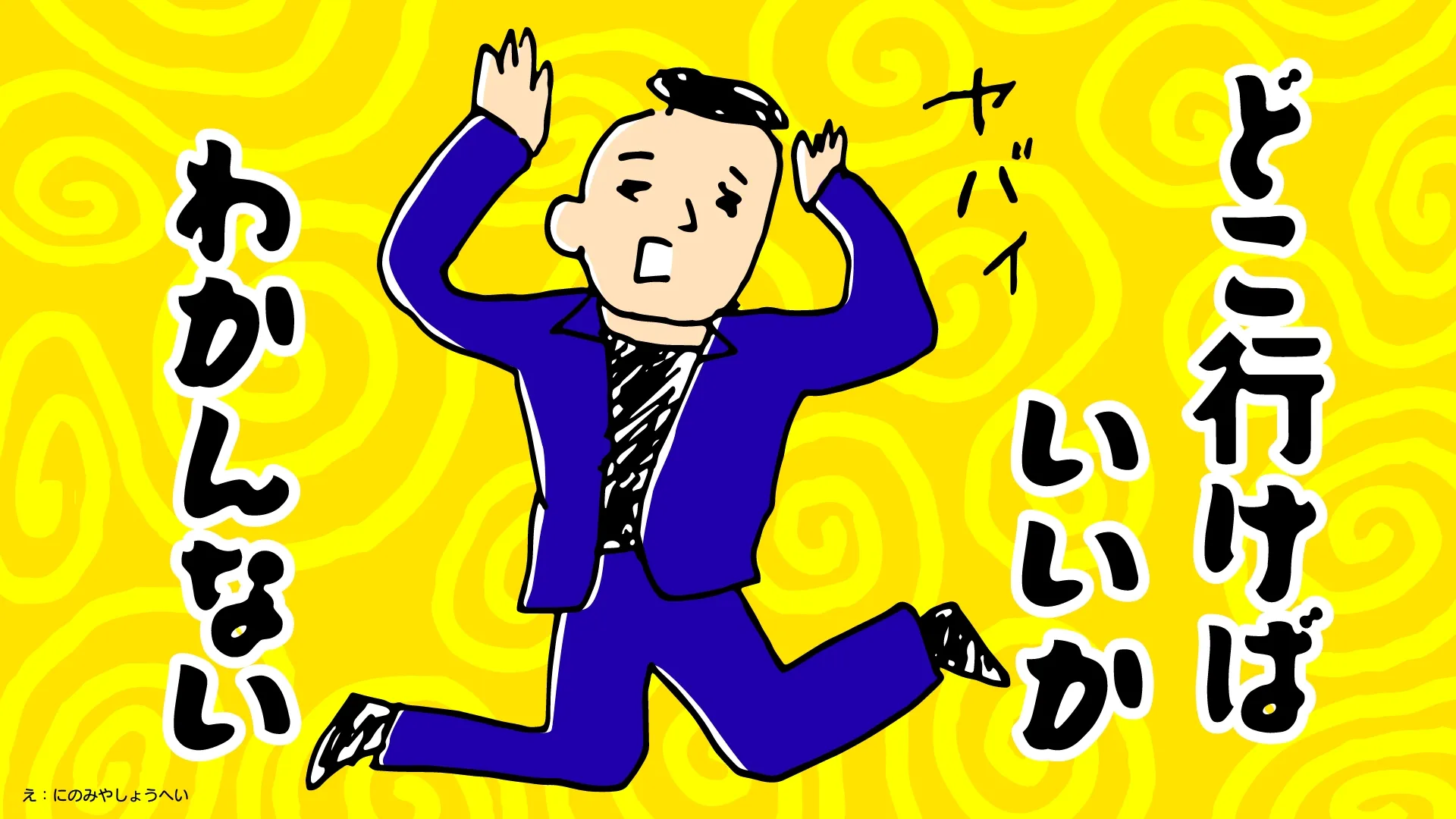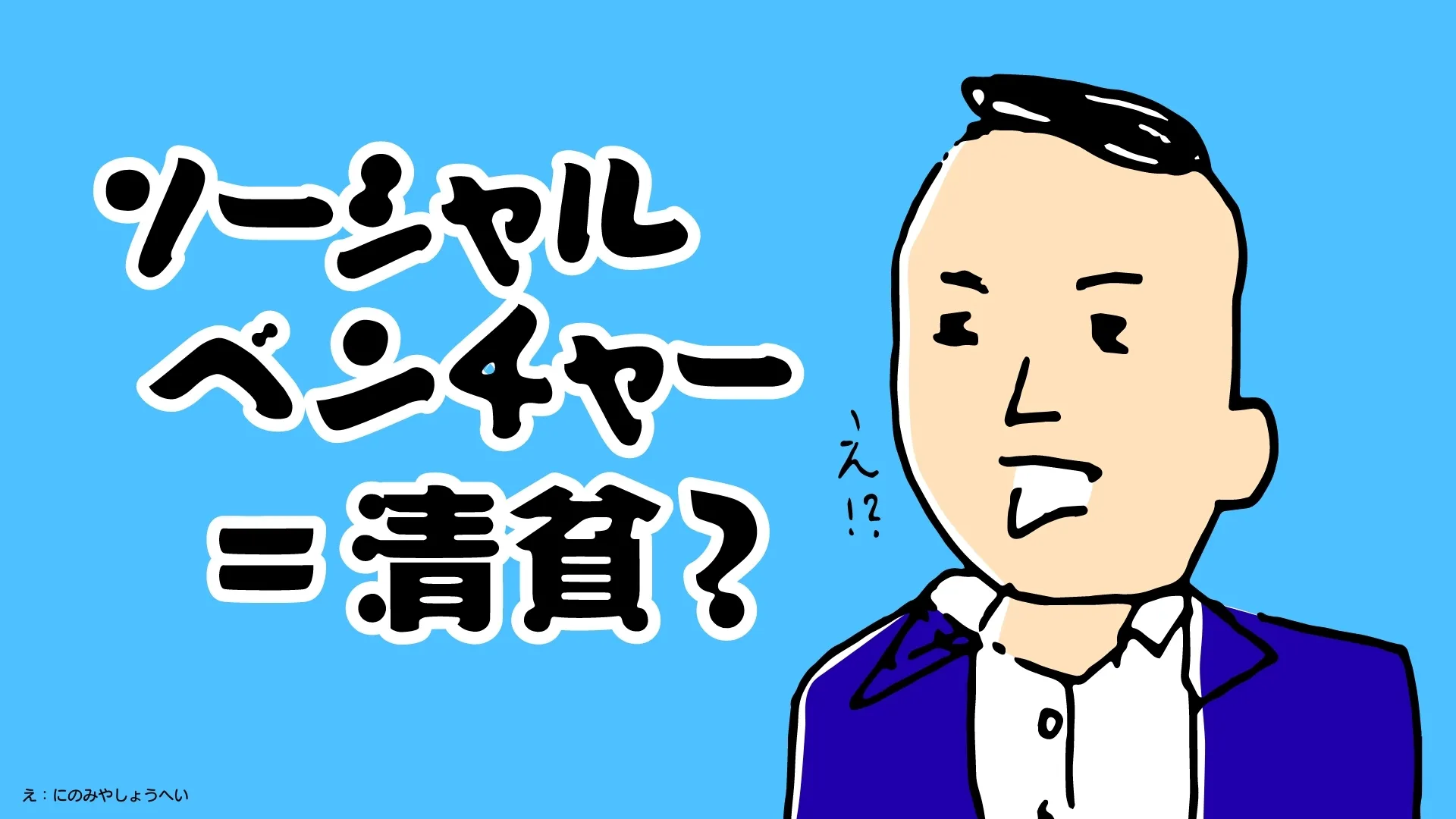【音楽の話】米津玄師のライブで得たものは?
「音楽の感情を理解するってどういうこと?」
米津玄師のライブを観て「曲の感情を理解する」ことが分からないことに気付き、音楽の感じ方について考察。
サッカーや麻雀では感動できるのに、なぜ音楽では難しいのか。
その理由を探る中で、音楽に「長調=明るい」「短調=悲しい」といったルールがあることを知り、アーラリンクのテーマ曲の解説を聞きながら音楽の仕組みや曲に込められた工夫を学び、「音楽の聴き方」を見直します。
- 目次
- 米津玄師のライブに行ってきた
- 音楽の感動がわからない!?
- 経営者にセンスは必要か?
- 音楽の感じ方をロジックで学ぶ
- スポーツには感動できるのに?
- 音楽とスポーツの違いとは?
- アーラリンクのテーマ曲を解説してもらう
- 音楽は背景とセットで楽しむもの
米津玄師のライブに行ってきた
米津玄師のライブに行ってきました。実は僕にとって初めての男性アーティストのライブだったんですよ。過去にオタクの友達に連れられて、アイドルのライブに行ったことはあったんですけど、いわゆる「ミュージシャン」のライブは今回が初めてでした。
嫁さんが音楽好きで、今回のライブチケットも応募して当てたんです。で、ライブに行って思ったのは「すげぇな」ってこと。米津玄師がマイクを客席に向けたりして、お客さんと一体になって歌う姿は初めて見る光景でした。歌うのが本当に上手いし、ライブパフォーマンスのクオリティが高いんですよね。
一番感動したのは、彼のMCでした。「徳島の片田舎でバンド活動がうまくいかなかった自分が、ニコニコ動画に出会って、そこから自分の音楽を発信し始めた」という話をしていて。ネットの向こうにいる誰かに届いていた音楽が、今こうやって目の前の大勢の人と共有できている。それがすごく嬉しいって話していて、めちゃくちゃ感動しましたね。
音楽の感動がわからない!?
でも、ライブ全体を通して、「音楽の感情を理解する」っていうことが僕にはよく分からなかったんです。嫁さんが「この曲にはこういう感情が込められているんだよ」って教えてくれるんですけど、僕は「そうなの?」って感じで、正直ピンとこなかったんですよね。
そこで気づいたのが、僕には「音楽のセンス」がないってこと。歌や踊りがどんな感情を表現しているのかを感じ取る力が弱いんですよ。会社のホームページやオフィスのデザインを考える時もそうなんですけど、僕は「かっこいい」「おしゃれ」っていう感覚がいまいち分かってないんじゃないかって、ちょっと危機感を覚えました。
経営者にセンスは必要か?
経営者って、苦手を作っちゃいけないと思うんです。別にすべて得意である必要はないけど、デザインとかアートのセンスがゼロだと、事業のブランディングにも影響するじゃないですか。
うちの会社のホームページも、かっこいいデザインにはなっていると思うんですけど、それが本当に僕らが表現したいものを伝えられているのか、正直分からないんですよ。経営者として、もっと「伝える力」や「表現のセンス」を磨かないといけないなって思いましたね。
音楽の感じ方をロジックで学ぶ
そんな話をしていたら、二宮さんに「音楽ってロジックで説明できるんですよ」って言われました。
例えば、音楽には「長調」と「短調」があって、長調は明るい曲調、短調はちょっと切ない曲調になるらしいんですよね。で、「Lemon」は短調で作られていて、悲しみを表現している、と。
なるほど、音楽の構造にはちゃんとロジックがあるんだなって思いました。例えば、短調の曲は悲しい感じに聞こえて、長調の曲は明るく聞こえる。そういう理論があるなら、僕みたいに感覚的に理解できない人間でも、学べば少しは分かるようになるんじゃないかって。
でも、嫁さんからは「いや、それ以前に、分かろうとする努力をしていないだけじゃない?」って言われたんですよね(笑)。確かに、音楽を深く聞く習慣がないし、歌詞や曲調の意味を考えたこともなかったかもしれない。でも、それを知ることで、もう少し音楽を楽しめるようになるのかも。
音楽とスポーツの違いとは?
スポーツには明確なルールがあるし、試合の流れがある。それを理解しているからこそ、感情移入できるんじゃないかと思うんです。でも音楽は、決まったストーリーがない。自由に感じ取っていいものだからこそ、僕みたいに「どう感じればいいのか分からない」っていう人もいるんじゃないですかね?
二宮さんも「スポーツ好きな人はスポーツに感動するけど、音楽好きな人は音楽に感動する。両方同じくらい好きな人は少ない気がする」って言ってて、すごく納得しました。
でも、経営者って苦手なものをそのままにしておくわけにはいかないんですよね。だからこそ、音楽やアートのセンスも、もう少し磨かないといけないのかなって思ったりもします。
アーラリンクのテーマ曲を解説してもらう
そんな話の流れで、二宮さんが作った「スーパークレイジーソーシャルベンチャー」のテーマ曲の解説をしてくれました。実はこれ、AI作曲ツールを使って作られた曲らしいんですよね。
歌詞は「I’m Super Crazy Social Venture, I’m ALALINK」みたいなフレーズを軸に作っていて、メロディの雰囲気も「マーベルっぽくてかっこいいもの」に寄せてるらしいです。
で、実際に曲を流しながら解説を聞いたら、「おお、なるほど、確かにかっこいいな!」って思いました。自分がさらっと聞いたときには分からなかったけど、ちゃんと意図を知ると「あ、ここで盛り上げるように作ってるんだな」とか「ここはちょっと静かになって、また盛り上がるんだな」みたいなことが分かるんですよね。
音楽は背景とセットで楽しむもの
結局、音楽の良さって「単体で理解しろ」って言われても難しいんじゃないかと思いました。例えば映画の主題歌だったり、アニメのオープニングだったり、何かのストーリーとセットになることで、感情が引き出されるんですよね。
米津玄師の「Lemon」も、彼のおじいちゃんが亡くなったときに作った曲ってい う背景を知ると、より切なく感じるし、「KICK BACK」もチェンソーマンのオープニングだからこそあの雰囲気が際立つ。そう考えると、音楽単体じゃなくて、何かの文脈の中で楽しむのが大事なんじゃないかって思いました。
音楽の聴き方を学ぶ
今回の話で気づいたのは、僕は今まで「音楽を理解しよう」としたことがなかったってことです。でも、スポーツや麻雀のように、背景を知ることで楽しめるなら、音楽もロジックやストーリーを学べば、もっと楽しめるようになるかもしれない。
アーラリンクのテーマ曲だって、ただ聴いてるだけじゃなくて、どういう意図で作られたのかを知ると、より深く楽しめるようになった。だからこれからは、音楽をもっと意識的に聴いてみようと思います。