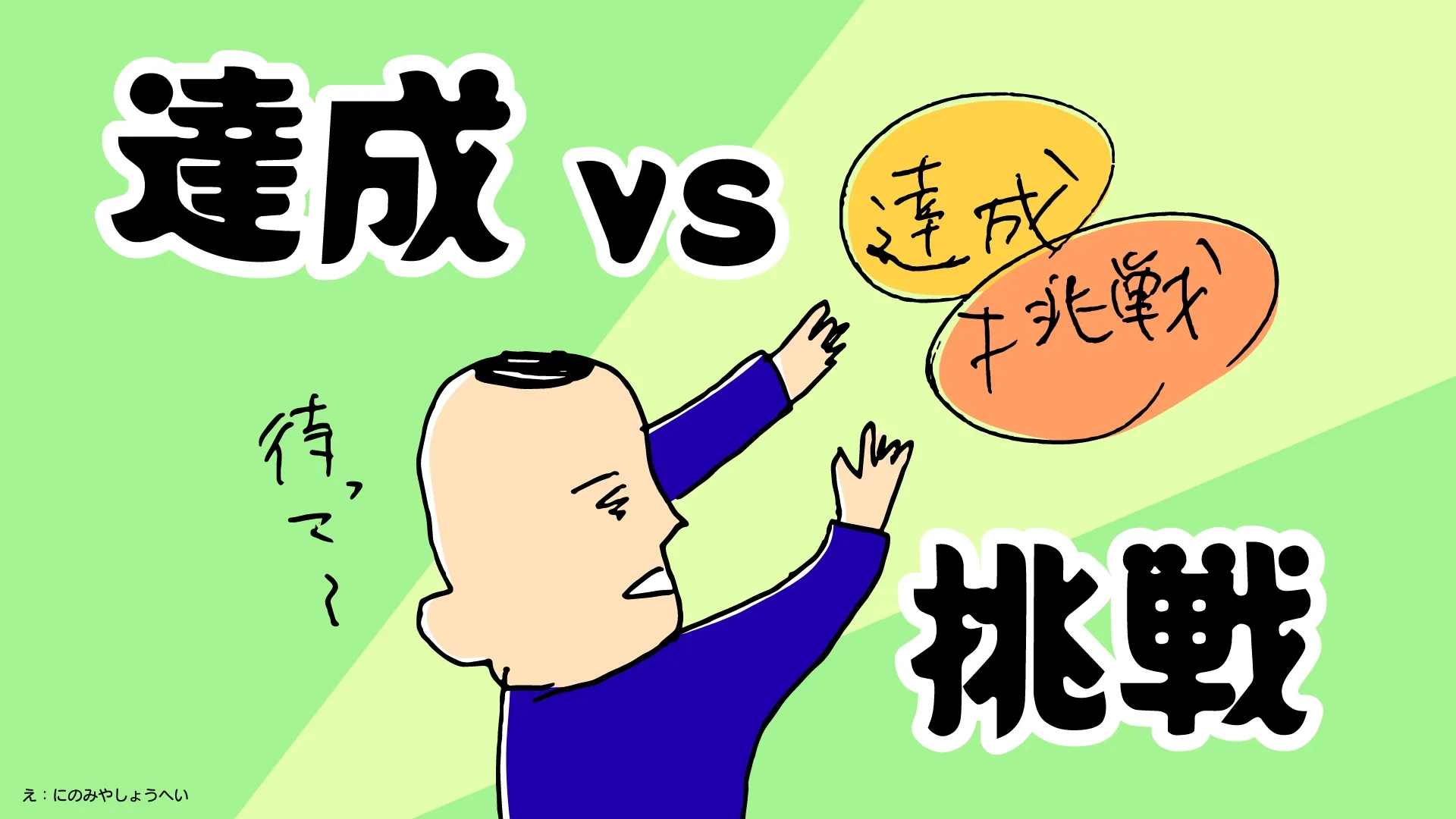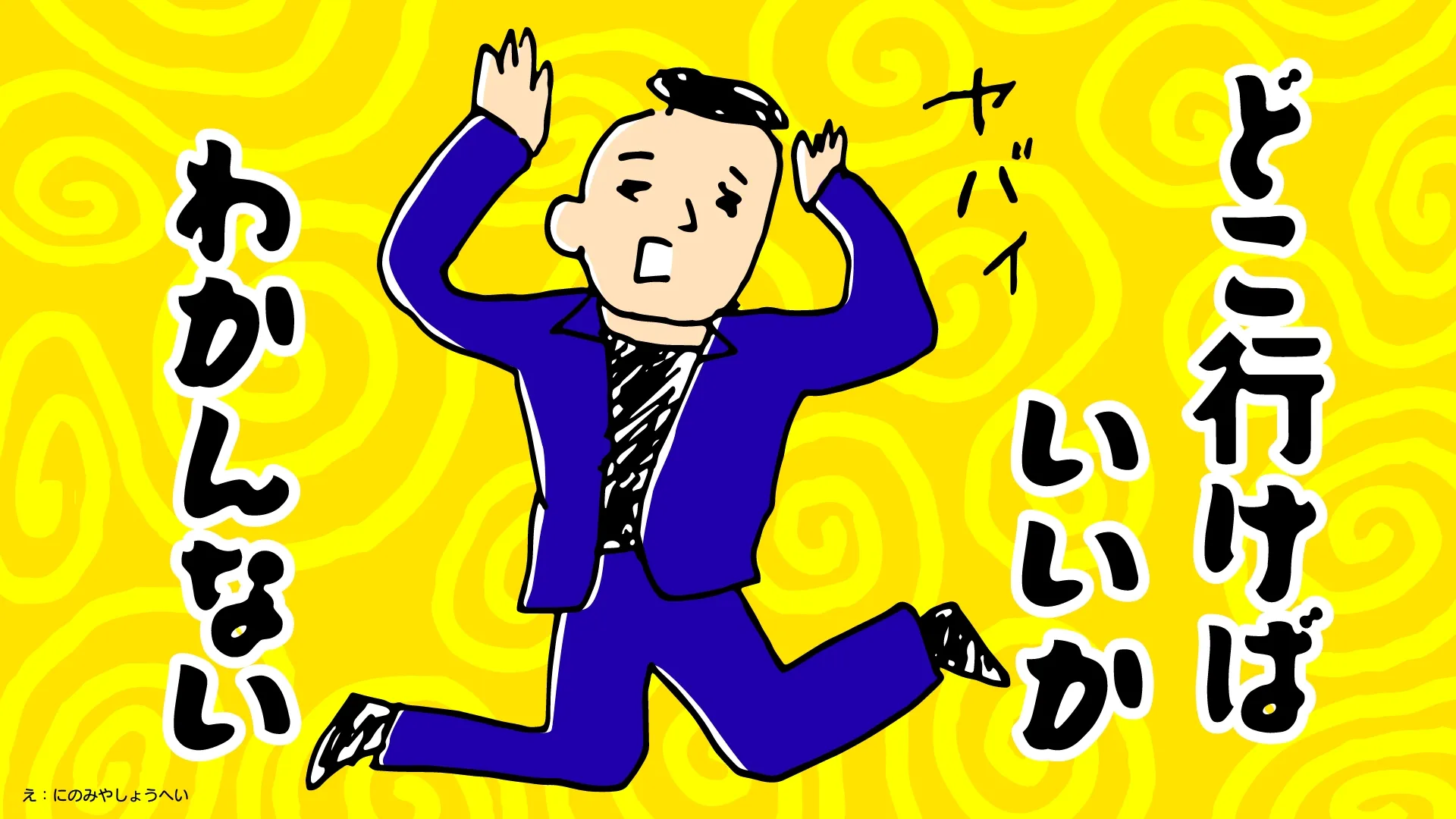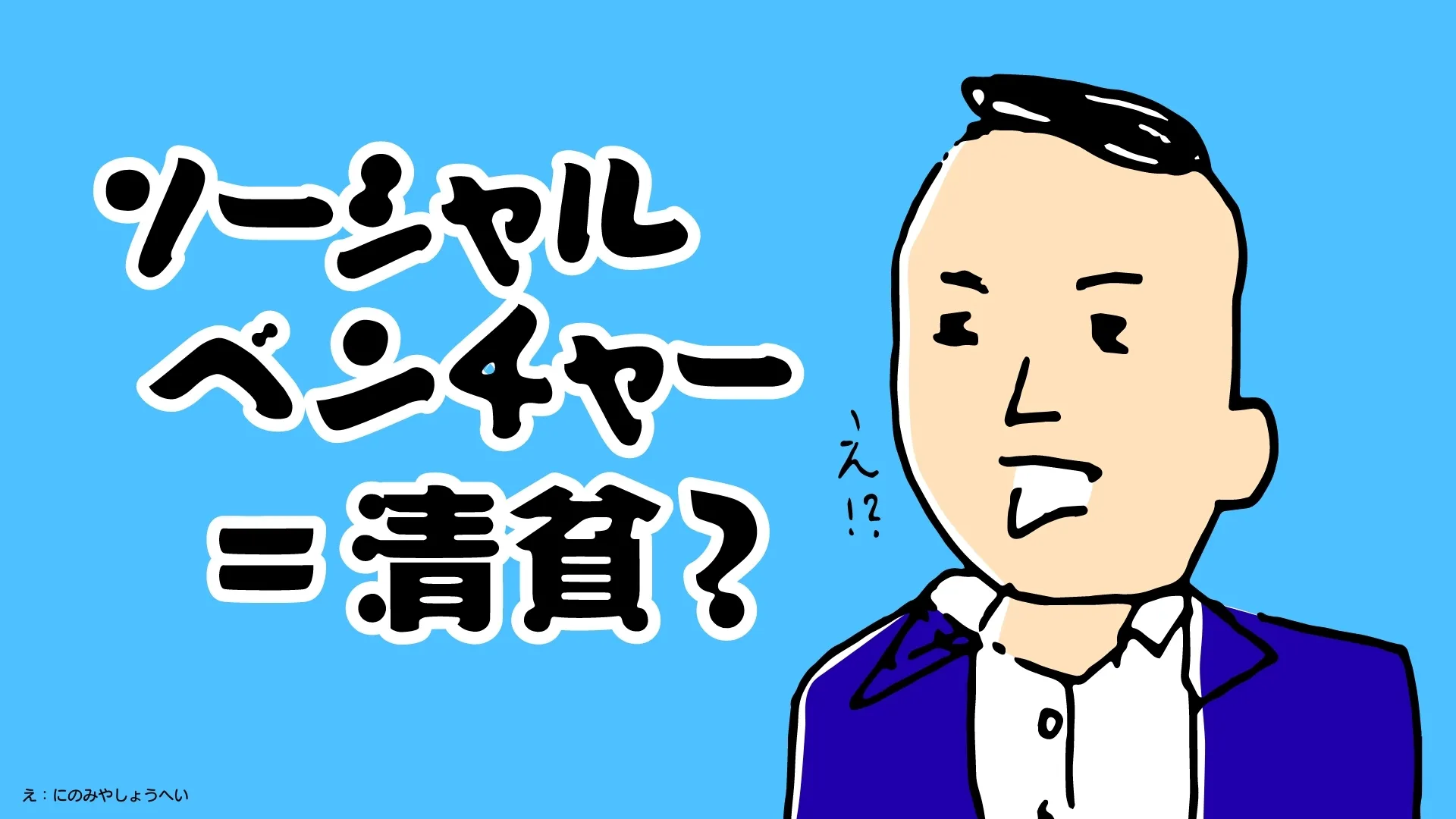【アーラリンク 会社の歴史編】CS運用:大事な仕事ほど外部に頼んではいけない!
「大事なのはスピード感、外に頼んでしまうとそれが失われてしまう」
CS業務で学んだ「大事な仕事ほど社内でやらなければならない」ことのお話でした。
難しい・時間がかかる業務は外部に頼んで行っていたことに対する違和感・スピード感が今後の業務・体制に大きな影響を与えてしまう可能性を伝えていきます。
- 目次
- 俺たちはスーパークレイジーなソーシャルベンチャー
- 創業初期のカスタマーサポートは地獄だった
- データベースを自作したら革命が起きた
- 外注したら大失敗した話
- AIチャットボットを秒でやめた話
- 人間の対応が持つ価値
- 50人規模のカスタマーサポート体制
- 継続することの大切さ
- 「辛い仕事」を外に出すのは違う
- カスタマーサポートの未来
俺たちはスーパークレイジーなソーシャルベンチャー
どうも、高橋翼です。今回も始まりました、スーパークレイジーソーシャルベンチャー。日本を下から支えるというミッションで、困窮問題に取り組むアーラリンクの創業者である僕が自由に語る番組です。よろしくお願いします。
なんかね、この「スーパークレイジーソーシャルベンチャー」ってタイトル、最初は自分で言うのがちょっと恥ずかしかったんですけど、だんだんかっこよく思えてきました。ベジータのギャリック砲みたいなテンションで言いたいんですけど、まだそこまではいけてないですね(笑)。でも、タイトルがかっこいいと気分も上がります。
前回に引き続き、今回も僕の事業の歴史について話していこうと思います。特に、カスタマーサポートの話ですね。これがもう、大変だったんですよ。
創業初期のカスタマーサポートは地獄だった
創業から5年目ぐらいまでは、僕自身もカスタマーサポートの電話に出ていました。しかも、データベースなんてものはなく、Excelで管理してたんですよ。とにかく大変で、もう地獄でしたね。
で、事業が成長して社員が10人弱ぐらいになった頃、さすがにExcel管理に限界が来たんです。データベースというものが世の中にあるらしいぞ、と気づいて、そこからめちゃくちゃググりました。で、「どうやらデータベースを導入すれば、この苦しみから解放されるのでは?」って思ったんですよね。
でも、問題があって。発注するにしても、僕には「こういうのを作ってほしい」と明確に伝える能力がなかった。だったら、自分で作るしかないなってことで、もう一度カスタマーサポートの電話を受けながらエンジニアとしてデータベースを作ることになりました。
データベースを自作したら革命が起きた
結果、自分でデータベースを作ってみたら、もう業務の効率が爆上がりしました。Excelから卒業できた瞬間、感動しましたね。全員が同じ画面を見れて、パソコンから情報を入力できるようになって、しかもリアルタイムで更新される。まさに革命でした。
でもね、これに5年かかったんですよ。もし発注していたら、かなりの費用がかかっていたはずです。でも、自分で作ったことで、そのノウハウが社内に蓄積されて、今もその仕組みが脈々と受け継がれています。これはやって本当に良かったですね。
ただ、当時は完全にエンジニアになってましたね。経営者っていうより、エンジニア兼カスタマーサポートのオペレーター(笑)。経営が止まってたわけじゃないけど、もうほぼエンジニア業務に没頭してました。でも、そのおかげで「どういう情報が必要で、どういう仕組みを作るべきか?」っていう要件定義能力がめちゃくちゃ上がったんです。今、新規事業を考えてるんですけど、またデータベースを作ることになりそうですね。もう慣れたもんですよ(笑)。
外注したら大失敗した話
7期目ぐらいの時、カスタマーサポートを外注しようと思ったんです。「オペレーション業務は外部に任せて、社員はもっとクリエイティブな仕事をしよう!」みたいなノリで。完全に、どこかの効率化の本に影響されてましたね。
結果、1ヶ月で撤回しました。
まず、外部のオペレーターさんが、うちのサービスに対して「魂」を持っていないことに気づいたんです。やっぱり、僕らのサービスを説明するのは、僕ら自身じゃなきゃダメなんですよね。ちょっとしたニュアンスとか、「いや、それ違うんだよな」っていうズレが気持ち悪くて。
それに、スピード感が失われるんです。社内なら「こう変えました」ってすぐ伝えられるのに、外部に委託すると「これを変更しました」→「マニュアルに落とし込みます」→「研修します」→「運用開始」っていう無駄な工程が増える。これがもう、耐えられなかった。
それに、そもそも外部の人に任せるってことは、「自分がやりたくない仕事を誰かに押し付けてるだけじゃないか?」って気づいたんです。辛い仕事だから外注するって、結局誰かがその辛さを背負ってるんですよね。それなら、自分たちで責任持ってやるべきだなって思いました。
だから、1ヶ月で「やっぱ戻そう!」って決断して、そこから半年かけて巻き取りました。めちゃくちゃ大変でしたけど、今では本当にやってよかったと思っています。
AIチャットボットを秒でやめた話
で、もう一つ。AIチャットボットも導入したことがあるんですけど、これも秒でやめました(笑)。
一時期、チャットボットが流行ったじゃないですか。「問い合わせ対応の効率化!」みたいなノリで。でも、実際やってみると、お客さんが本当に知りたいことって、検索しても分からないから問い合わせてるんですよね。
で、実はお客さん自身も「何を知りたいのか」明確に分かってないことが多いんです。なんとなく「困ってる」から電話する。それをAIが解決できるかっていうと、無理なんですよね。
それに、スマホの音が出ないとか、ちょっとした不具合って、「ただマナーモードになってただけ」とか、人間が察して解決することが多いんです。そこをチャットボットで対応するのは難しすぎる。
結局、「やっぱ人間だよね」ってことで、チャットボットは即撤退しました。
人間の対応が持つ価値
カスタマーサポートって、単に「問い合わせに答える」だけの仕事じゃないんですよね。僕たちが大事にしているのは、人が人に対応することで生まれる価値なんです。
たとえば、お客さんが「スマホの音が出ない」と困っているとします。でも、それが単にマナーモードになっているだけだったら、AIの自動対応ではうまく解決できないことが多いんです。そういう場合、人間なら「もしかして、マナーモードじゃないですか?」って気づいて、すぐに解決できる。
僕たちが目指しているのは、ただ問題を解決するだけじゃなくて、ホスピタリティを持って対応すること。電話をかけてきたお客さんが、「なんかこの対応、気持ちよかったな」って思ってもらえるようにするのが重要なんです。
だからこそ、僕たちはAI対応に頼らず、人の手で対応し続けることを選びました。確かにAI化すれば効率は上がるかもしれません。でも、「効率が上がる=お客さんにとって良いこと」とは限らない。むしろ、機械的な対応をされたことで、お客さんがストレスを感じる可能性もある。だったら、人間がしっかり対応するほうがいいじゃないですか。
カスタマーサポートの品質向上を徹底する
僕たちのカスタマーサポートは、単なる「電話対応」じゃなくて、品質管理にもめちゃくちゃ力を入れています。
今は、対応の品質を数値化して、日々改善を重ねるということをやっています。具体的には、毎日すべての対応を振り返り、点数をつける。そして、その点数を元にフィードバックをして、少しでも対応品質を上げていく。
「どれくらいの品質を目指しているの?」って聞かれることがあるんですけど、目標は偏差値70くらいのレベル感です。ほぼトップクラスの品質を目指しているってことですね。
さらに、今では90点レベルの対応を目標にしているんですよ。でも、これがめちゃくちゃ大変なんです。毎日、毎回の対応を細かく振り返って、「今日はどうだったか?」をチェックしているので、もうPDCAを回しまくっている状態です(笑)。
でも、こうやってクオリティを上げていかないと、「ただ電話を取ってるだけ」になっちゃう。それじゃ意味がない。お客さんにとって価値のある対応をするためには、細かい改善の積み重ねが必要なんです。
50人規模のカスタマーサポート体制
今、うちのカスタマーサポートは50人規模で運営しています。社員だけじゃなく、いろんな形の雇用形態のメンバーがいるんですけど、やっぱり大事なのは「この仕事に対するマインドセット」ですね。
最近は、「ただ仕事をする」ではなく、「お客さんに価値を届ける」ことを意識した採用をしているんです。たとえば、以前は「カスタマーサポートの仕事は感謝されることが多い」という点を前面に出して採用していました。でも今は違います。
今は、「お客さんに感謝される前に、自分からエネルギーを与える存在になろう」というメッセージを伝えています。単に「クレーム対応をする仕事」じゃなくて、**「お客さんの1日をちょっと良くする仕事」**なんですよね。
採用基準も、昔は「トラブルを起こさない」「空気を読む能力が高い」とかが重視されていました。でも、今はそれに加えて、「どうやったらお客さんの気持ちが良くなるかを考えられるか?」という視点を持った人を採用するようにしています。
「辛い仕事」を外に出すのは違う
最初にカスタマーサポートを外注しようとしたとき、社員が疲弊しているから、辛い仕事を外に出そうという考えがありました。
でも、冷静に考えると、それってただ「辛い仕事を誰かに押し付けているだけ」なんですよね。自分たちが辛いからといって、外部のオペレーターさんにその負担を回してしまうのは違うんじゃないかって思ったんです。
「カスタマーサポートが大変だから、外注して楽になろう」というのは、一見すると合理的な判断に思えます。でも、うちのサービスを一番よく知っているのは僕たち自身だし、僕たちこそが、お客さんに対して一番良い対応ができるはずなんです。
だから、「自分たちの仕事を自分たちでちゃんとやる」という結論に至りました。
カスタマーサポートの未来
これからも、僕たちはこのカスタマーサポートのクオリティを上げ続けていきます。機械的な対応ではなく、ちゃんと人間の温かみを持って対応するということを大事にしていきたいですね。
一部では「カスタマーサポートはAIに置き換えられる」って言われています。でも、僕はそうは思いません。確かに、機械で処理できる部分もあるかもしれない。でも、お客さんが本当に求めているのは、「自分の悩みにちゃんと寄り添ってくれる対応」なんです。
だから、うちは最後の最後まで人が対応するカスタマーサポートを続けます。そして、ただ対応するだけじゃなくて、「お客さんの1日が少しでも気持ちよくなるような対応」をしていきます。