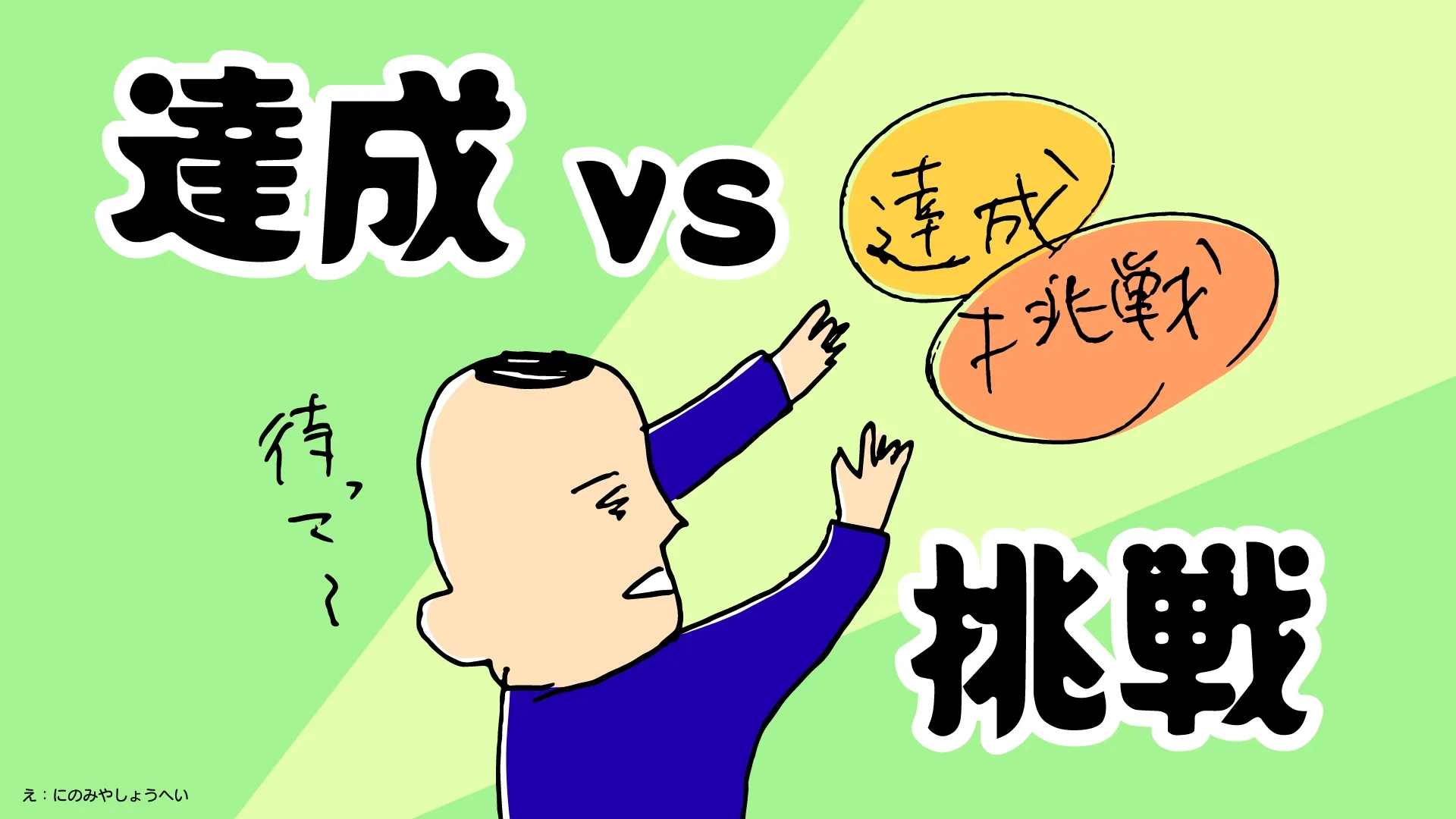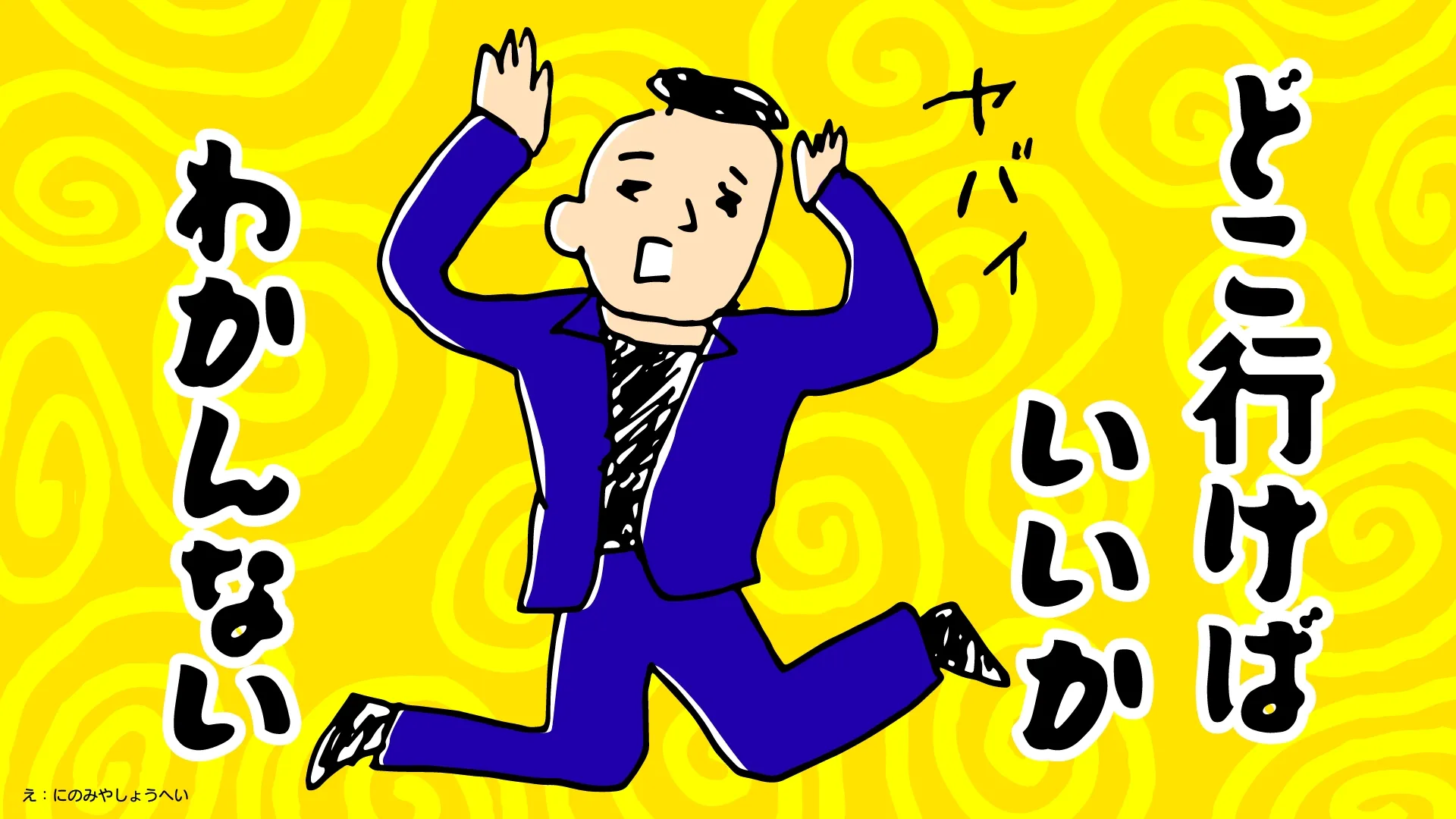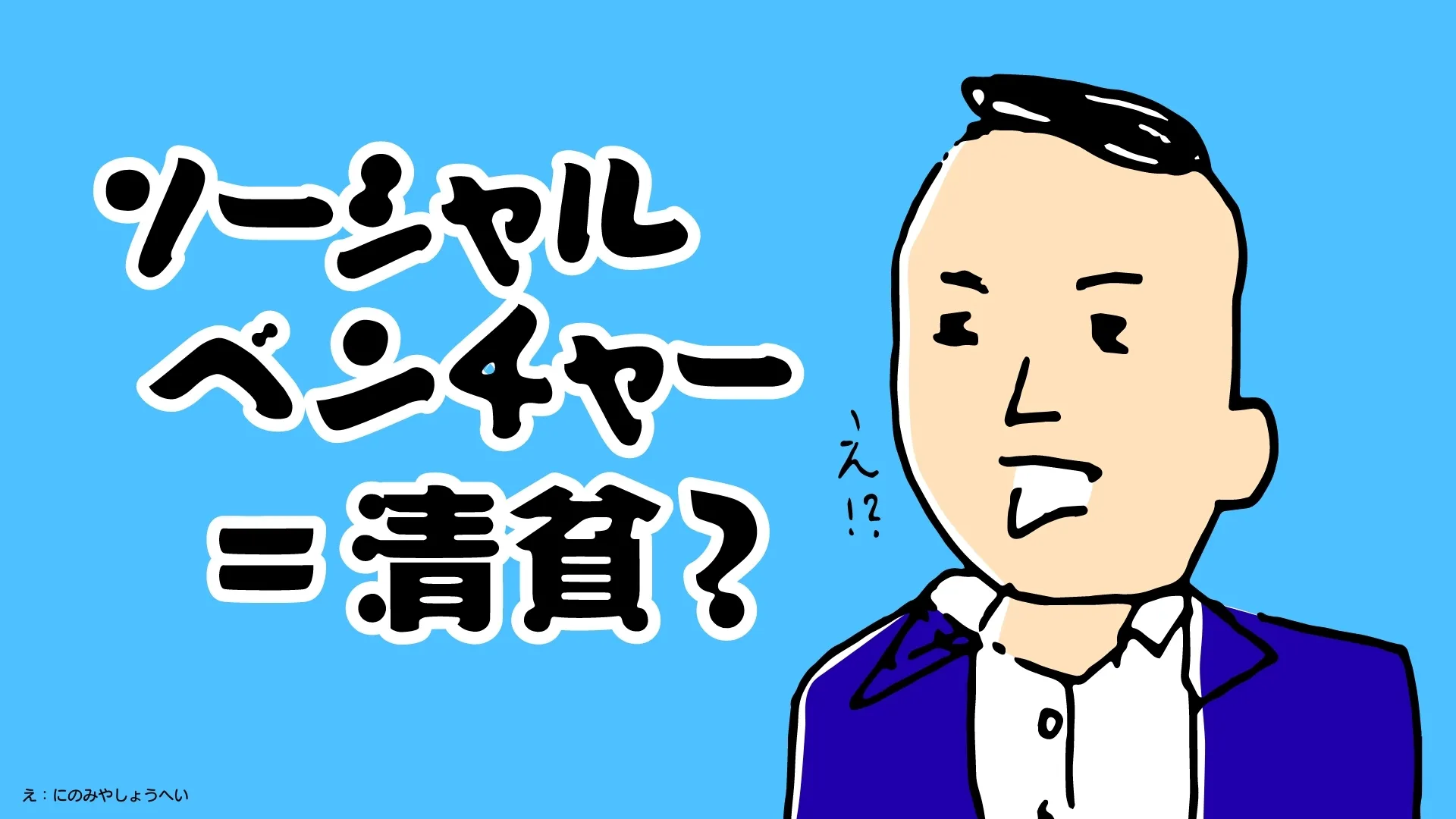【アーラリンク会社の歴史編】CS運用の話
「今の社長は雇用生み出しているだけでは古い!」
カスタマーサポートの意識はどの会社でも活かすことができる心構えとなっていますので勢お聞きいただければと思います!
- 目次
- スーパークレイジーなソーシャルビジネス
- 「雇用してる=社会貢献」はもう古い?
- 社長は「老害」になってはいけない
- 僕のカスタマーサポートの歴史
- エクセル地獄の顧客管理
- カスタマーサポートのリアルな現場
- いつまで電話対応をしていたのか?
- ビジネスホンからCTIへ進化
- まとめ:カスタマーサポートの歴史は会社の歴史
スーパークレイジーなソーシャルビジネス
突然ですが、タイトルを「スーパークレイジーソーシャルビジネス」に変えてみました。正直、自分でもよく分かっていません(笑)。でも、名前負けしないように頑張ります!
僕の考えている世界観って、サムネには全く反映されていないんですよね。確かに、熱量とビジュアルのギャップがすごい。サムネ変えたいな…いや、むしろサブタイトルをどうにかしたほうがいいかも?
前回のラジオや動画でも話したんですけど、僕らはスーパークレイジーなソーシャルベンチャーをやってるんですよ。でも、まだ平熱モードなので、これからどんどんテンション上げていきます!
今回のラジオ、テーマもちゃんとあるんですが、その前にちょっと小話をさせてください。
「雇用してる=社会貢献」はもう古い?
昨日、新しく顧問になってくれる方と話していて、めちゃくちゃ衝撃を受けたんです。その方は社会の変革を考えるプロで、内閣にも関わっていたような人。そんな人が言ったのが、「雇用を生み出してる社長は偉い」っていう考え方が、もう古いって話でした。
要は、今後は労働者がどんどん減っていく時代。なのに「雇用を生み出す=社会貢献」って考え方のままだと、むしろ社会の足を引っ張ることになる、と。
例えば、5人でやる必要のない仕事を、5人でやらせていたら、それって社会にとって非効率ですよね? その余った3人を別の仕事に回して、日本全体の生産性を上げなきゃいけない。社長はただ雇うだけじゃなくて、もっと生産性を意識して組織を作らないと、逆に「社会悪」だって言われる時代が来るぞって話でした。
これを聞いて、本当に衝撃でしたね。「雇用を生んでるから社会貢献してる」っていう考え方が、もう通用しない時代に入ってるんだなって。
しかも、単純に人を減らせばいいって話じゃなくて、例えば「週2日しか働けない人」や「障がいを持ってる人」が仕事に参加できるように、業務を作り変えるとか。そうやって、労働市場に参加できていない人たちを巻き込んでいくのも、経営者の役割になっていくんじゃないか、って話も出て。
こういう視点を持ってる社長って、どれくらいいるんだろう? たぶん、まだまだ少ないんじゃないかな。
社長は「老害」になってはいけない
今まで「俺は雇用を生み出してるんだ!」って誇りに思ってた社長が、実は「社会悪」になりかねない時代。むしろ「余計な人員を抱えている経営者=老害」って言われるかもしれない。
これ、めちゃくちゃ考えさせられましたね。
確かに、労働人口は増えてるんです。でも、それは女性や高齢者の社会進出によるもので、これ以上増えることはない。だから、今後は「1人あたりの生産性をどう上げるか?」が、経営者の重要なテーマになっていく。
「10人でやってる仕事を5人で回せるようにしろ」っていう時代が、もう来てるんですよね。だから、何十人も低賃金で雇うんじゃなくて、少数精鋭でしっかり給料を払って、社会全体の生産性を上げることが求められてる。
これ、社長にとっては相当なプレッシャーですよね。でも、そうしないと、日本全体が弱くなっちゃう。
僕もこの話を聞いて、「やばっ…もっと考えないと」って焦りました。経営者として、もっと真剣に生産性の向上に取り組まないといけないなって。
この話だけでラジオ1本いけるくらいの衝撃でした(笑)。
僕のカスタマーサポートの歴史
さて、本題に入ります。今日は「会社の歴史編」として、カスタマーサポートの話をしようと思います。
僕が起業して13年目。個人事業の期間も含めると14年目になりますが、実は起業した瞬間からカスタマーサポートをやっていました。
最初のカスタマーサポートは、なんと僕の携帯電話。固定電話じゃなくて、完全に個人の携帯でお客さんの対応をしてたんですよね(笑)。
移動しまくってたので、改札で電話を取ったり、駅のホームで折り返したり…。環境的にはめちゃくちゃ悪かったです。でも、どこにいてもお客さんの対応をしなきゃいけなかったので、仕方なかったんですよね。
その後、社員やアルバイトを雇うようになって、やっとビジネスホンを導入。最初は普通の内線電話でした。でも、僕自身が大学時代にビジネスホンを売る仕事をしてたので、「自分が売ってたものを導入する社長になったんだな〜」ってちょっと感慨深かったですね(笑)。
当時は電話回線も8回線くらい。今は60〜70回線入れて、本格的なコールセンターになっています。
エクセル地獄の顧客管理
当時のカスタマーサポート、電話対応も大変だったんですけど、もっとヤバかったのが顧客管理。
最初はエクセルで管理してたんですよ。でも、スプレッドシートじゃなくてローカルのエクセルだったので、同時編集ができない。
2000人以上のデータをエクセルで管理してたんですけど、数式もバリバリ入れてたので、重すぎて動かなくなることも多々ありました。しかも、誰かが編集してると他の人が触れないという地獄(笑)。
「誰がどこを編集してるか分からない問題」とか、「保存し忘れてデータ消えた事件」とか、色んなトラブルがありましたね。
今はちゃんとシステム化されてますけど、当時は本当に手作業でした。社員6人くらいの時代だったので、それでもなんとか回してましたね。
カスタマーサポートのリアルな現場
当時のカスタマーサポートは、電話対応だけじゃなくて、顧客管理のエクセル問題も相当ヤバかったんですが、実際の対応業務もなかなか過酷でした。
特に大変だったのが、お金の支払いができないお客さんの対応と、携帯が使えなくなったお客さんの対応。この2つは、今も昔も変わらずカスタマーサポートの大きな課題なんですよね。
お金の支払いができないケースでは、「どうにかならないか?」と交渉されることが多くて。これはもう、まさに水際の攻防戦です。もちろん、僕らもできる限りの対応はするんですけど、最終的には「払ってもらわないとどうにもならない」という現実があるので、そこを伝えるのが本当に大変でした。
もう一つの「携帯が使えなくなった」系の問い合わせも、電話サポートだと難易度が高い。お客さんの画面を見れない状態で「このボタンを押してみてください」とか「設定を確認してください」とか言うのって、めちゃくちゃ大変なんです。
しかも、携帯が壊れているのか、単なる設定ミスなのか、勘違いなのかが分からないことも多い。音が出ないっていうトラブルも、「単に音量がゼロになってるだけ」っていうパターンも結構あるんですよね。でも、お客さんとしては「壊れた!」って思い込んでるから、なかなか話が噛み合わない。
実際、こういうケースで「交換しますね」と言って端末を送ると、100台中80〜90台は壊れていないってこともあるんです。つまり、交換対応のほとんどが不要なものだったりする。
だから、カスタマーサポートとしては「たぶん壊れてないので、まずは確認しましょう」と丁寧に説明したい。でも、お客さんは「早く交換してくれ!」と思ってる。ここにギャップが生まれて、難しい対応になることが多かったですね。
いつまで電話対応をしていたのか?
実は僕、自分で電話対応をやっていた期間が結構長いんですよね。
10年前から5年前くらいまでは、普通に現場で電話を取っていました。その後、一旦は経営に専念する形になったんですが、実は「誰でもスマホ」の立ち上げの時もまた電話対応をやってたんです。
だから、5年くらい現場から離れてたけど、2年くらい前にはまた3ヶ月〜半年くらい電話に出てました。つまり、創業初期から今に至るまで、何度か最前線に戻って対応してるってことですね。
カスタマーサポートって、やっぱり会社の顔なんですよ。だから、現場の感覚を持っていることってすごく大事だなと思っています。
ビジネスホンからCTIへ進化
電話対応の仕組みも、最初は僕の個人携帯から始まって、次にビジネスホンになって、今ではCTI(コンピューターと連携した電話システム)を使うようになりました。
ビジネスホン時代は、4人くらいの社員やアルバイトで対応していて、内線で連携を取ってました。でも、やっぱり業務が増えてくると、それだけでは限界があるんですよね。
今はCTIを導入して、60〜70回線で運用しています。完全にコールセンター化していて、当時の規模とは全然違います。
昔は「電話回線って2〜3回線あればいい」って感覚だったんですが、今の規模を考えると、当時の自分が見たら驚くと思います(笑)。
まとめ:カスタマーサポートの歴史は会社の歴史
こうやって振り返ると、カスタマーサポートの歴史は、僕の会社の成長の歴史そのものなんですよね。
・創業当初は、僕の個人携帯で対応
・その後、社員が増えてビジネスホンを導入
・エクセルで顧客管理(これが地獄だった)
・今ではCTI導入で、コールセンター並みの規模に
カスタマーサポートの業務も、電話対応から始まり、顧客管理、トラブル対応など、どんどん進化してきました。
次回は、カスタマーサポートの歴史の続きを話そうと思います。今回話したのは、創業から5年目くらいまでの話なので、まだ10年分くらいのエピソードが残ってます(笑)。