LTV改善と聞くと、単なるビジネス戦略の一環と思われがちですが、アーラリンクの取り組みはそれを超えた「社会課題への挑戦」でもあります。
「お金がなくても携帯を持ち続けられる社会を作る」——アーラリンクはこの大きなミッションに挑戦し続けています。
- 目次
- LTV(ライフタイムバリュー)とは何か?
- 解約の9割は「支払いの問題」
- 「お金がない」をどう解決するか?
- 誰でもスマホ経済圏の構築を目指す
- LTV改善の本質は「自立を支えること」
- 未来への展望——アーラリンクが目指す社会とは
LTV(ライフタイムバリュー)とは何か?
LTV(ライフタイムバリュー)は、企業が顧客一人あたりから得られる総収益の指標です。単価を上げる、利用期間を延ばすなどの方法で向上できますが、アーラリンクでは特に「解約率の低減」に重点を置いています。
私たちのサービスでは、単価を上げるよりも契約期間を長くすることがLTV改善の鍵になります。なぜなら、利用を継続してもらうことが、長期的な利益の最大化につながるからです。そのため「解約改善」を軸に取り組んでいます。

解約の9割は「支払いの問題」
携帯電話の解約理由を分析すると、驚くべきことに約9割が「お金がない」もしくは「支払いを忘れた」という理由に分類されます。
具体的には、6割のユーザーが「お金を持っていない」、3割が「支払いを忘れた」と答えています。
支払い忘れは口座振替の導入やリマインダー通知の強化などである程度解決できますが、より深刻なのは「お金がない」という問題です。これは単なるオペレーションの改善では解決できません。ここにイノベーションが必要なのです。
「お金がない」をどう解決するか?
支払いが難しいユーザーに向けて、私たちは複数のアプローチを検討しています。
例えば、電気やガスといった生活インフラの契約を代理で取り扱い、その手数料をユーザーに還元する仕組みがあります。ユーザーが電気やガスを切り替えると、アーラリンクが手数料を受け取り、それを「誰でもスマホポイント」として携帯料金の支払いに充てることができるようにします。
また、ポイ活の仕組みを活用し、アプリのインストールや特定のサービス利用で得られるポイントを携帯料金に使えるようにすることも考えています。こうした仕組みを整えることで、「お金がないから解約するしかない」という状況を減らすことができます。
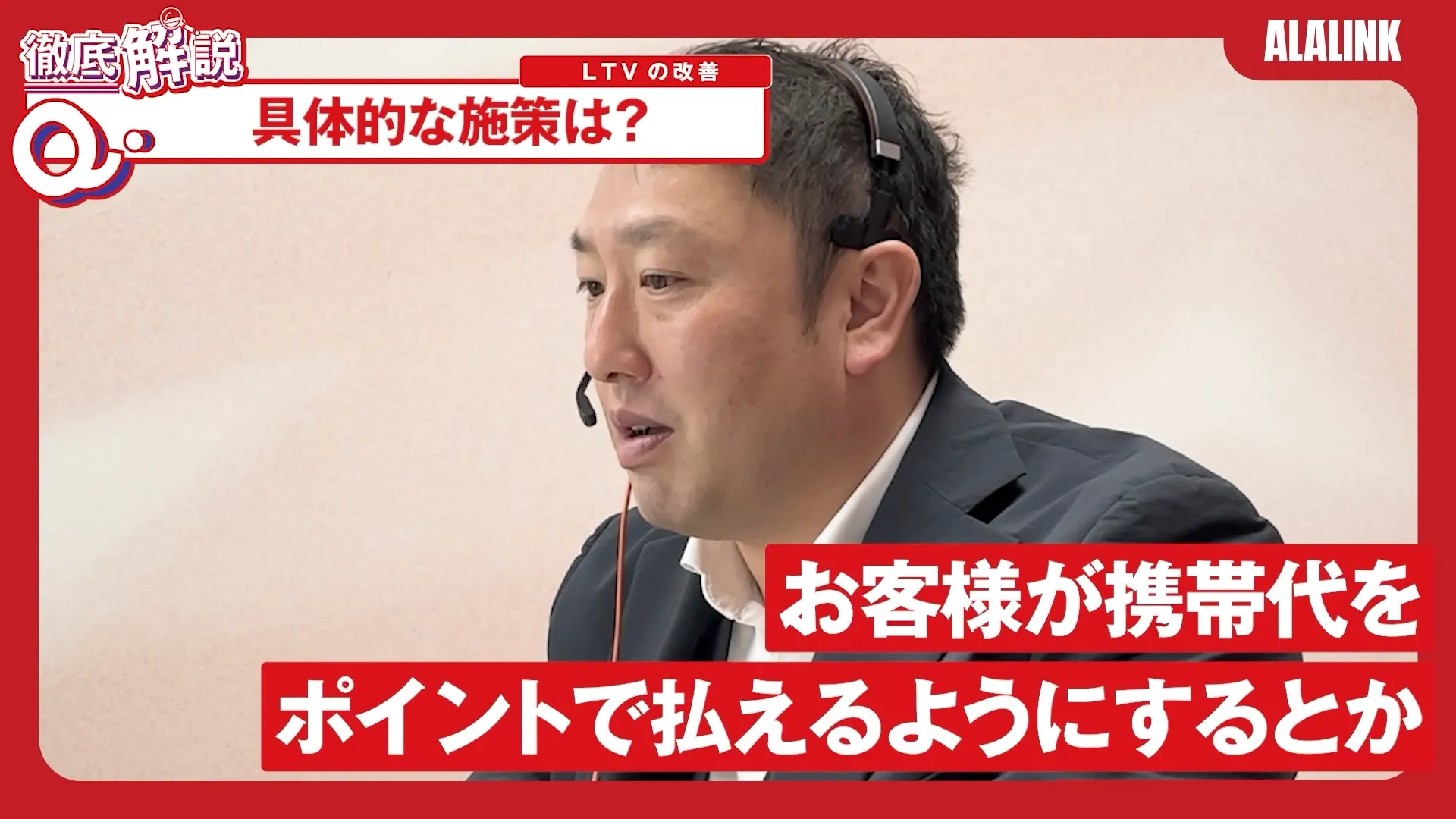
誰でもスマホ経済圏の構築を目指す
まずは代理販売の形でスタートし、効果が見込めるものがあれば、自社で事業の上流を担うことも視野に入れています。例えば、電気やガスの提供元になることや、ポイ活サービスを独自に展開することも考えられます。
さらに、就労支援の仕組みを作ることも重要だと考えています。「働きたくない」「働けない」といった人に対して、どうすれば働きやすくなるのか、あるいは社会貢献をしながら対価を得られる仕組みを作れるのかを模索しています。
生活保護などの公的支援に頼ることも必要ですが、それを前提としたサービス設計にはしたくありません。国の支援ではなく、自分の力で携帯料金を支払えるような仕組みを作ることこそが、本当の意味での自立支援になると考えています。
LTV改善の本質は「自立を支えること」
アーラリンクのLTV改善とは、単に解約率を下げることではなく、「経済的に困難な状況にある人でも携帯を持ち続けられる仕組みを作ること」です。そして、その根底にあるのは「自立を支える」という考え方です。
携帯電話は、今や生活の必需品です。仕事を探すにも、社会とつながるにも、スマホは不可欠です。そのスマホを持ち続けられるようにすることで、より多くの人が経済的な自立を果たせるようにしたいと考えています。
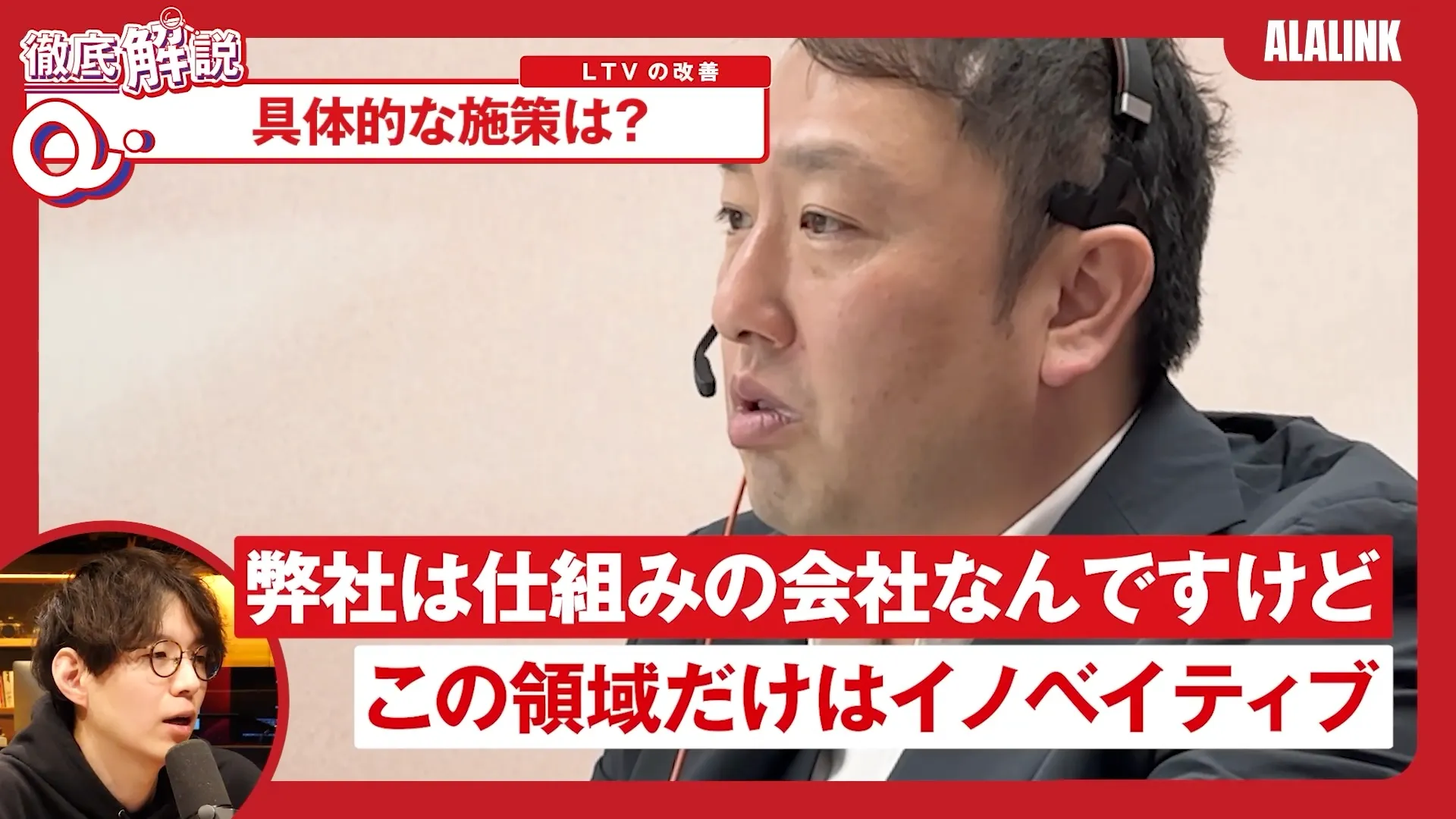
未来への展望——アーラリンクが目指す社会とは
最終的に目指すのは、「誰でもスマホ経済圏」の確立です。アーラリンクのサービスを利用することで、携帯料金を払えないという状況に陥らない仕組みを作る。そして、その仕組みを通じて、仕事をしたくない人が仕事をしたくなるような環境を作り、社会全体の活力を高める。
多くの企業が避ける「支払いが難しいユーザー」に正面から向き合い、国に頼らず自立できる社会を作る。この取り組みが実現すれば、アーラリンクだけでなく、社会全体にとって大きなインパクトをもたらすはずです。







