- 目次
- アーラリンクの始まりは社長一人のスタートから
- 社員が増えたら事件も増えた!? 6人の壁とは
- 仲良しこよしのカルチャーからの転換
- どうぶつの森事件とカルチャーの転換点
- 組織改革とリストラの決断
- 外向きの組織、顧客を中心に据えた経営へ
- アーラリンクの現在と未来。目指す組織像とは?
アーラリンクの始まりは社長一人のスタートから
──今日はアーラリンクのカルチャーの変遷について深掘りしていきます!まず、会社の始まりから教えてください。
高橋:アーラリンクの創業は2011年。組織として会社化したのが2013年ですね。でも、組織って言っても最初は僕ひとり。最初の数年間は完全に個人事業みたいな感じでやってました。
──完全に一人だったんですね。
高橋:そう。で、最初の社員が入ったのが2013年。ギャル気質の強いギャルだったんですよ。ギャルなんで言い方とかけっこう強くて「あれがない」「これがない」って言われたら、今なら無いのは当然だって言えるんですけど当時の僕は福利厚生を整えなくてはみたいな意識が強くなっていたと今は思いますね。
──なんか意外ですね。
高橋:初めて部下を育成するというのがその1人目の社員だったので、右も左もわからない感じで必要な機能を揃えていくみたいな印象が強かったです。
社員が増えたら事件も増えた!? 6人の壁とは
──最初の社員が入って、次に増えたのが……及川さん?
及川:そうですね、2016年の3月に入りました。ちょうど会社としては3年目くらいですね。
高橋:そうそう。最初は僕とギャルの社員、そして及川さんの3人だったんだよね。
──3人の時ってどんな雰囲気だったんですか?
及川:めっちゃバタバタしてましたね。社長とギャルの先輩がずっと電話対応や営業してて、私は経理とか事務作業を全部引き受けてました。
──そこからどんどん社員が増えていったわけですね。
高橋:うん。でも、ある時期から『6人目の社員が必ず辞める』っていう“6人の壁”みたいな現象が起き始めてね。
楠森:私が入ったのが2018年なんですけど、それまでに何人か辞めてたって聞いてました。
──6人目が必ず辞めるってどういうことですか?
及川:なんでしょうね……人が増えるたびに、システム化で切り替えるとかやりたいことも増えて、みんなキャパオーバーになって辞めていくみたいな感じでした。
高橋:そうそう。あと、採用の基準があんまりしっかりしてなくて、結局合わない人が入っては辞める、みたいなことが続いてた。

仲良しこよしのカルチャーからの転換
──その頃の社内の雰囲気ってどうだったんですか?
楠森:みんな仲がいい印象はありましたね。仕事終わったらみんなで飲みに行ったり、休みの日も遊んだり。会社のイベントでBBQとかもやってましたね。
高橋:その時は事業はうまくいっていたので、残業しないようにとか自由な社風にしようとか、世の中にもてはやされる会社の情報をキャッチしてそれを取り入れられないか考えるみたいな。
及川:人に残ってもらうためにはとか、そっちの方を考えていたかもしれないですね。
高橋:ただ、仲良しカルチャーからもっと仕事マインドというかお客様のために、社会のために、みたいな思いがあって、もっと強く行きたいなというのがあったので、7期目、2020年頃に飲み会行こうとか会社のイベントとか言わなくなったんですね。
及川:2020年頃の社長の変化は感じていました。社員の仲良しカルチャーが残っていましたが1年半くらいで切り替わっていったのかなと私自身は思っています。
どうぶつの森事件とカルチャーの転換点
高橋:そんな中で僕が決定的に『このカルチャーはダメだ』と思った瞬間があったんです。
──何があったんですか?
高橋:社内でみんなが“どうぶつの森”の話をしてたんだよ。しかも“会社のみんなでやってる”みたいな雰囲気で。
──え、ゲームの話がダメだったんですか?
高橋:いや、そうじゃなくて。会社が良くない方向のサードプレイス感になってしまっているような。会社って一生懸命お客さんとか社会のために事業して云々かんぬんって僕はすごい大事だと思っているんですけど、社員との間にものすごく乖離を感じたというか。
及川:当時はコロナ禍でコミュニティが会社しかなかったんですよ。でも仕事としてはそれはよろしくなかったなっていうのは今聞きながら反省してました。
高橋:なんか僕がコロナで困ってる皆の心の拠り所を批判してる奴みたいな(笑)
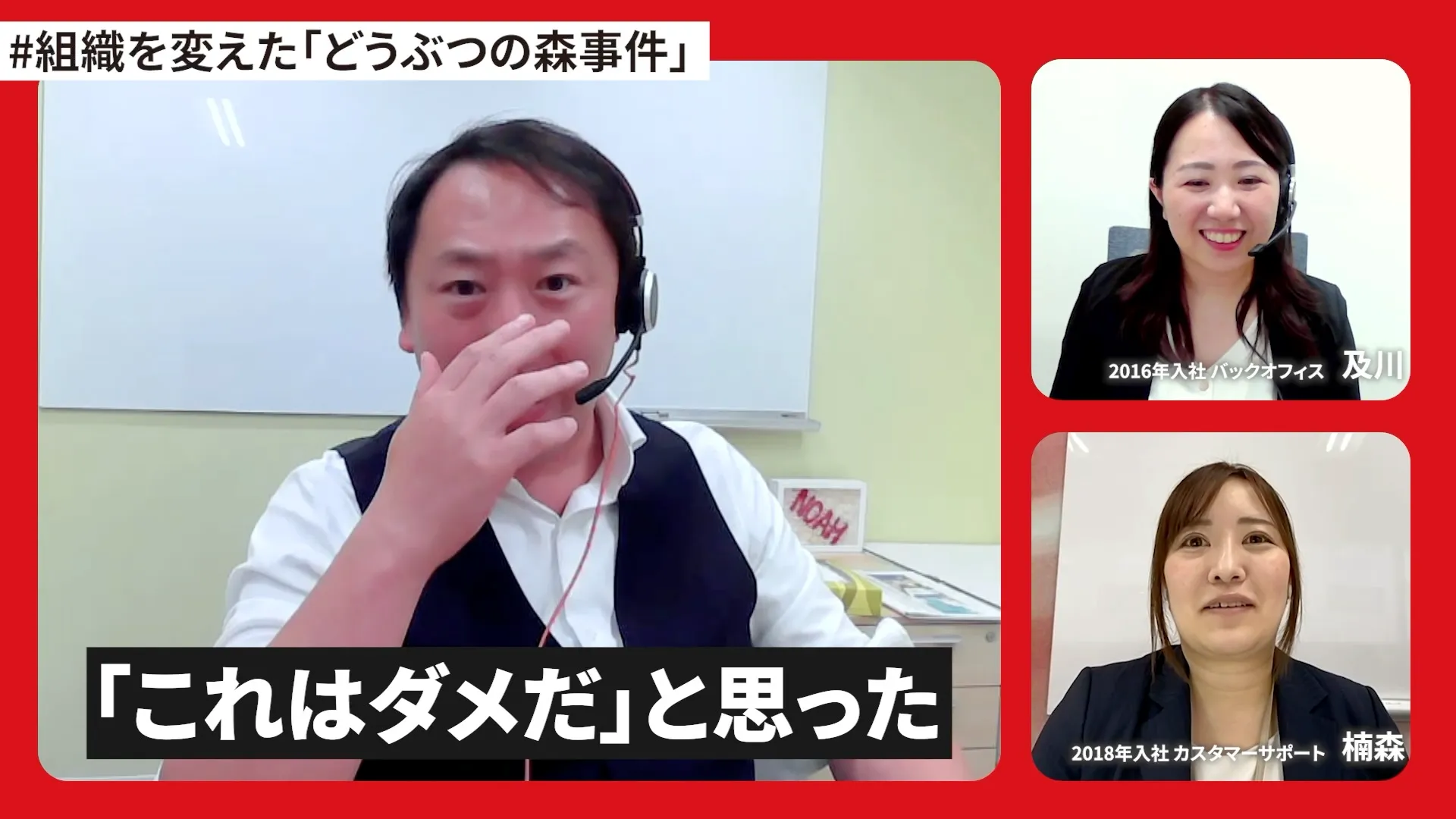
組織改革とリストラの決断
──そこからカルチャーを変えていくことになったわけですね?
高橋:当時新卒採用が始まって、上の層がこの感じだと下が育たないなって思って、ちょっとずつ会社の理念と合ってない人に対してごめんだけどっていう話をしていました。
──なんかちょっとリストラっていう表現をされてましたけど。
高橋:もう合わないからうちは辞めた方がいいんじゃないみたいな感じですね。それこそ“どうぶつの森”で結束してるくらい良いサードプレイスだったのに、彼らからすると「社長急に変わったな」という感じだろうし、恨まれたり嫌なことを言われるのもしょうがないなと思いました。僕も葛藤があったんですけど、このままじゃアーラリンクはダメだってすごく強く思ったので。
──社内の雰囲気はどうだったんですか。
及川:雰囲気的には最悪でしたね。
楠森:私の方も辞める人から相談を受けることが多かったですね。
及川:ただ、ここからどう乗り越えようかみたいな気持ちが多分全体的にはあったのかなと思います。
外向きの組織、顧客を中心に据えた経営へ
──当時、業績はどうだったんですか?
高橋:売り上げはめちゃくちゃ伸びてたんですよね。
及川:コロナの影響で逆に需要が伸びていました。
高橋:厚生労働省との連携とかもその時期に行われて。
──事業はめちゃくちゃ伸びてるのに社内の雰囲気は最悪っていう、社内が楽しい時より伸びちゃうみたいな。
高橋:そう。でも、それで確信したんです。“会社のモチベーション”と“業績”って、そんなに関係ないんじゃないかって。
──なるほど。
高橋:だから、会社の目指す方向性をガラッと変えた。“社員のための会社”じゃなくて“社会や顧客のための会社”にするって。
──ではこの9期目くらいが経営のやり方がガラッと変わっていくターニングポイントですか?
高橋:僕の考え方はその時でガラッと変わりましたね。で、そのときに衝撃を受けたのがドラッカーの“事業とは顧客創造活動”っていう言葉。『あれ? 顧客創造が事業なのになんでずっと内向きのことばっかり考えるんだろう? 顧客創造やってないじゃん』って思ったんです。
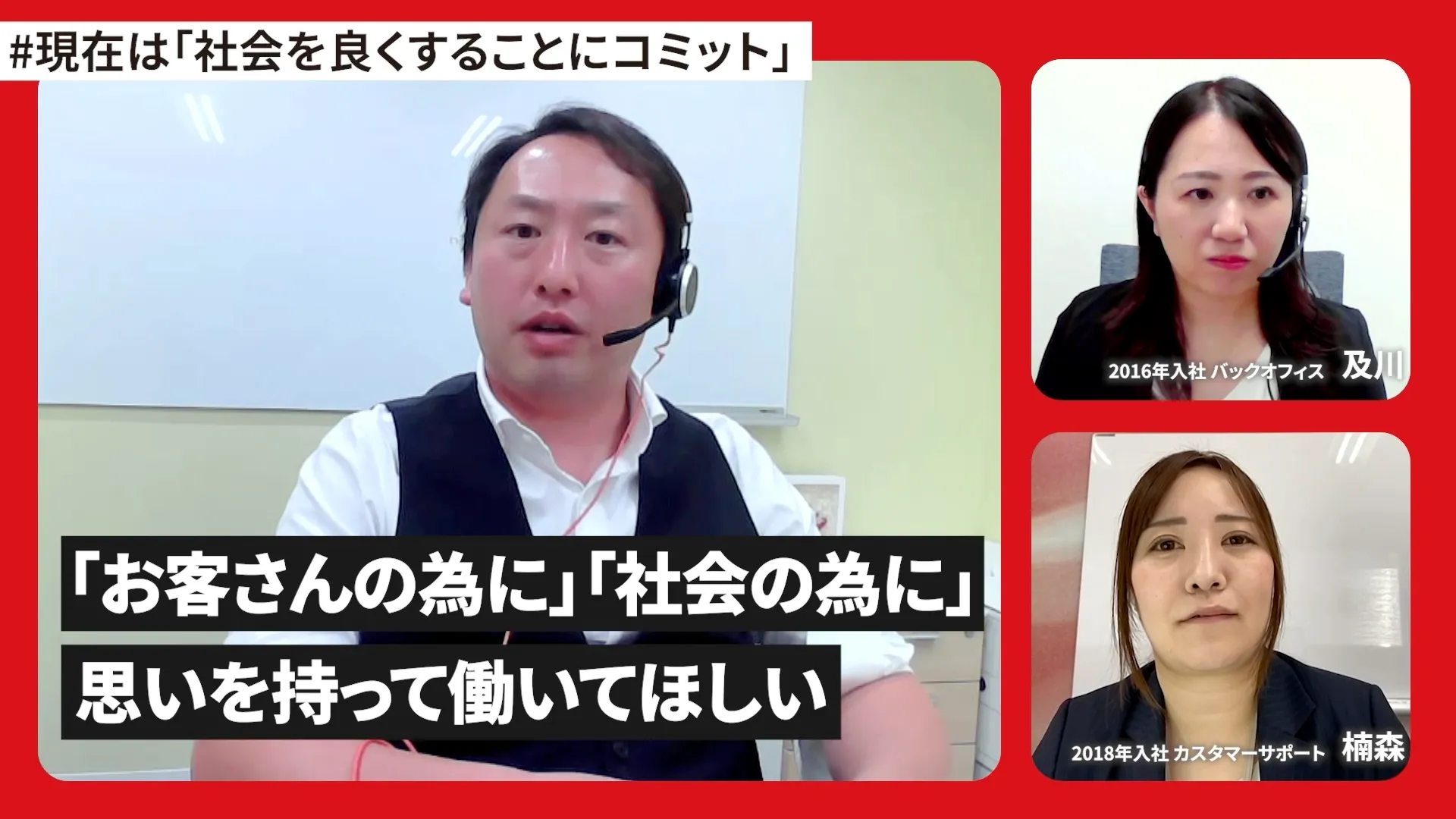
アーラリンクの現在と未来。目指す組織像とは?
──それから現在に至るわけですが、今のアーラリンクはどんな組織になっていますか?
楠森:顧客創造活動っていうところにも繋がるかなと思うんですけど、お客さんのためにとか社会の困っている人のために頑張れる人たちが傾向として今集まっているので、数年前のカルチャーとは全然違うものを感じていますね。
及川:社会貢献したいっていう人が今年は特にいっぱい入ってきている印象です。昔みたいな仲良しこよしな風潮ではなくなって、それは会社としてはすごくいい形かなと思っています。
楠森:いい意味でメリハリがついたというか会社らしくなってきて、新しいものに向かって動き出している感じはしていますね。
──主体性のある人が増えてきているんですか?
及川:もとから主体性がある人というより、誰かのために何かをしたい人って内向きというか自分が主役じゃなくてもいいっていう人が多いので入社当初は受け身なんですけど、仕事を通して裁量権を持たせてもらったり施策に打ち込むことで主体性を持って成長していったり色々発揮していく人が多い印象です。
──なるほど。最後に高橋社長、アーラリンクの今後の展望や思いを教えてください。
高橋:困っている人のために、社会のためにという活動ってけっこう選択肢が限られているんですよね。それが仕事としてできるということ自体をすごく大切にしたいなと思っています。だからそういうことを事業としてやりたい人と一緒に働いて会社を大きくして行きたいというのが今シンプルに一番強く、そのための土台はできたかなという感じがしています。
高橋:アーラリンクという会社が、社会貢献したいとか社会のためになりたいと思った時に、ここに来ればそれができるというプラットフォームでありたいなと思っています。そういう会社でありたいし、11年かけてそういう会社の目指し方の片鱗みたいなものを掴んでいる感じはしますね。
──この11年で人も考え方もやり方も、あらゆることが変わったんですね。
高橋:事業の外側が変化するのはいいんですけど内側の変化って、私の未熟なところに付き合ってもらっちゃってる感じなので、そこは本当に申し訳ないなと思いつつ、次に同じ失敗を繰り返さないとか、今思っていることを背骨にして進んでいきたいですね。
──この動画はこれからアーラリンクに入る人のためにカルチャーを話ましょうというテーマだったんですが、組織マネジメントのあり方、失敗と成功の秘訣みたいなセミナーを聞いている感じでめちゃくちゃ学びになりました。ありがとうございました。
高橋・及川・楠森:ありがとうございました。







