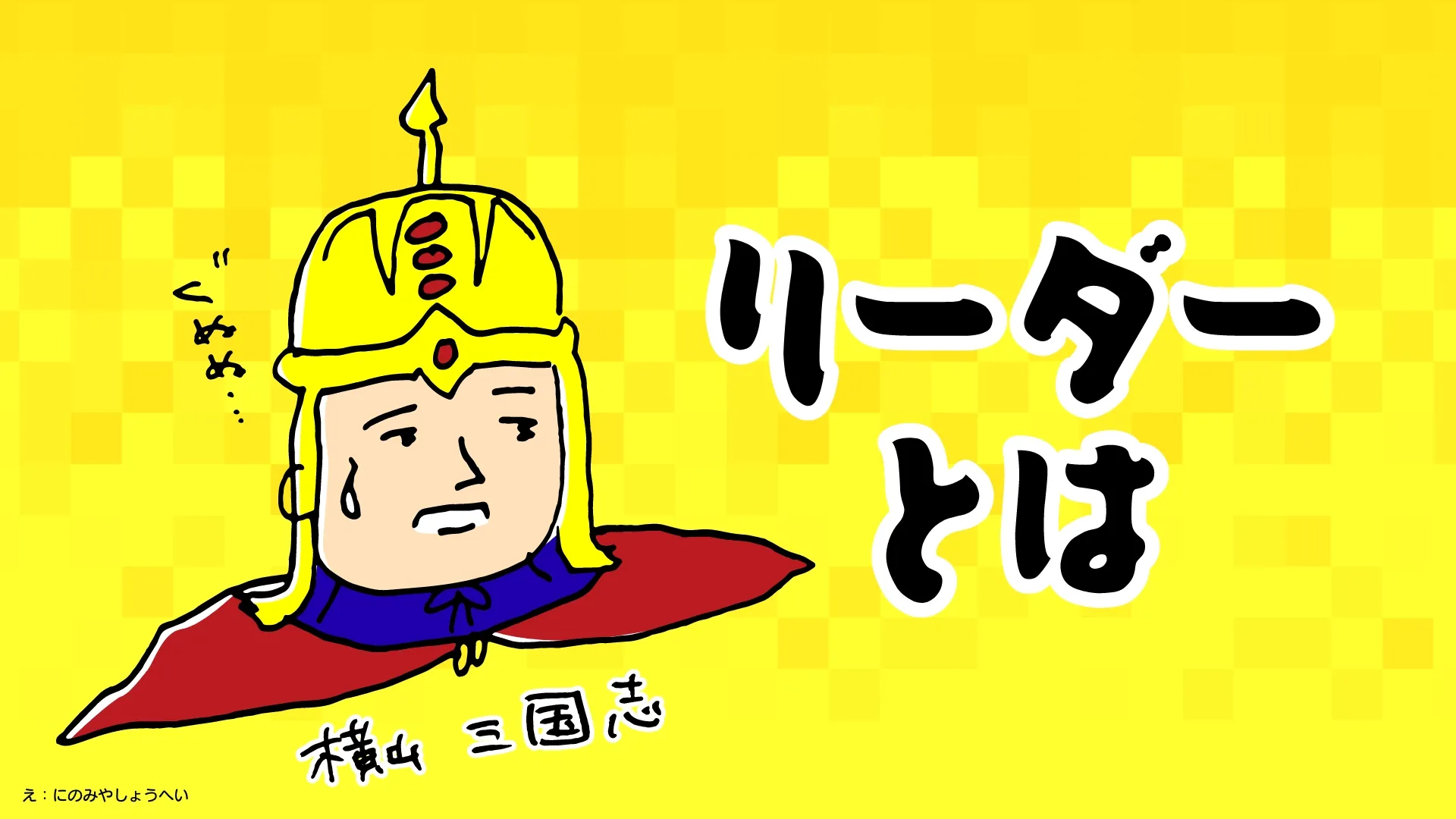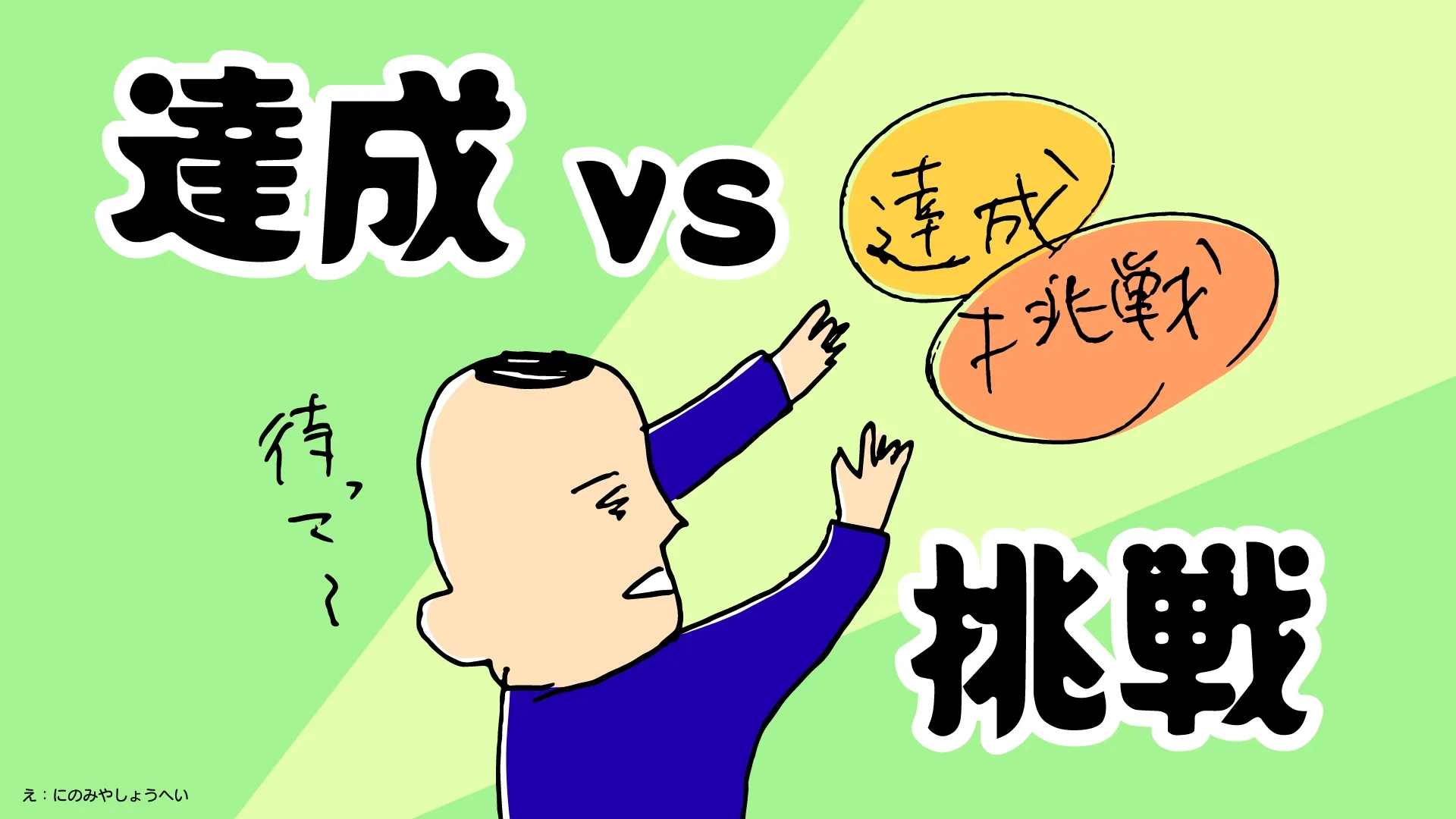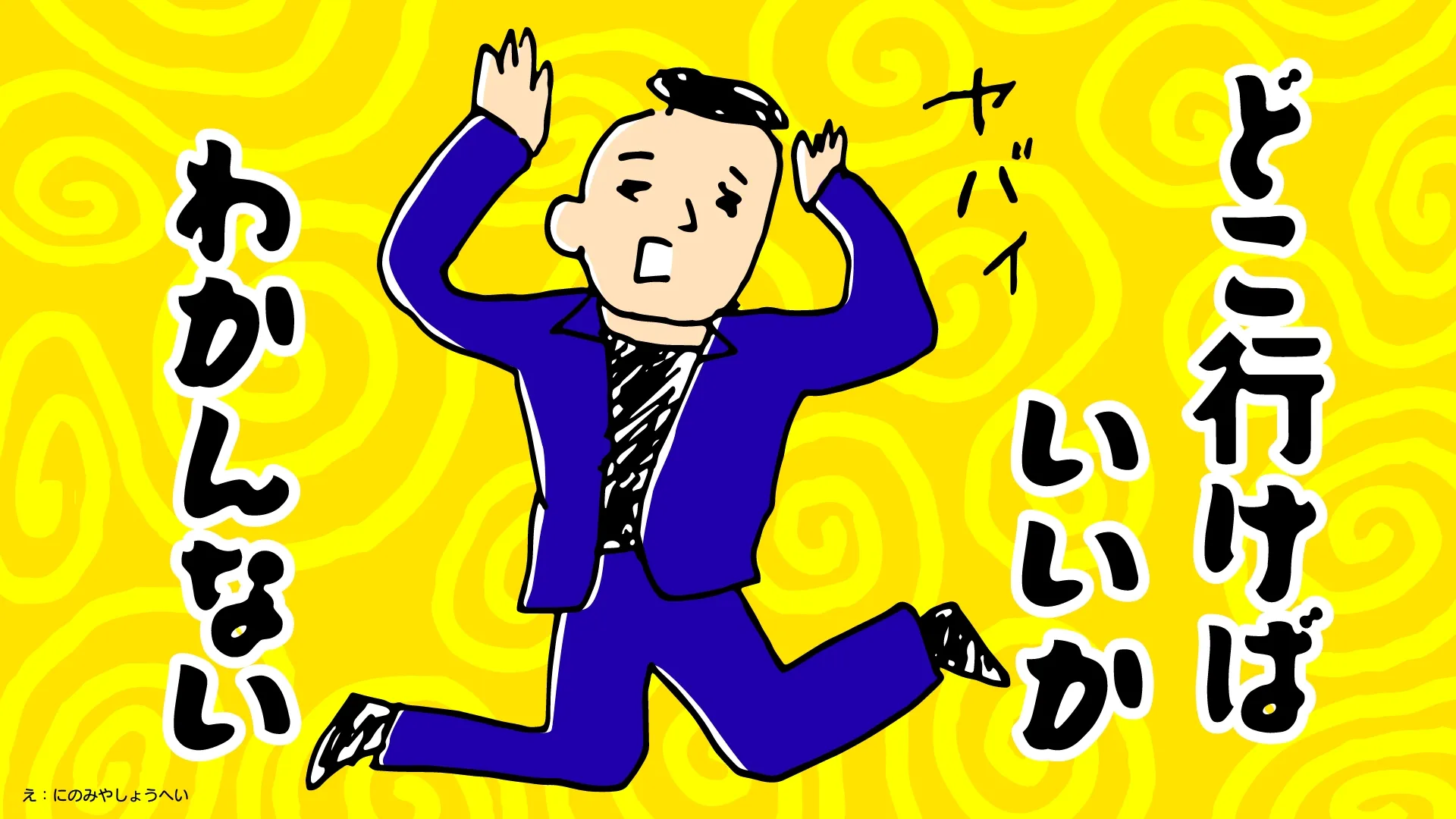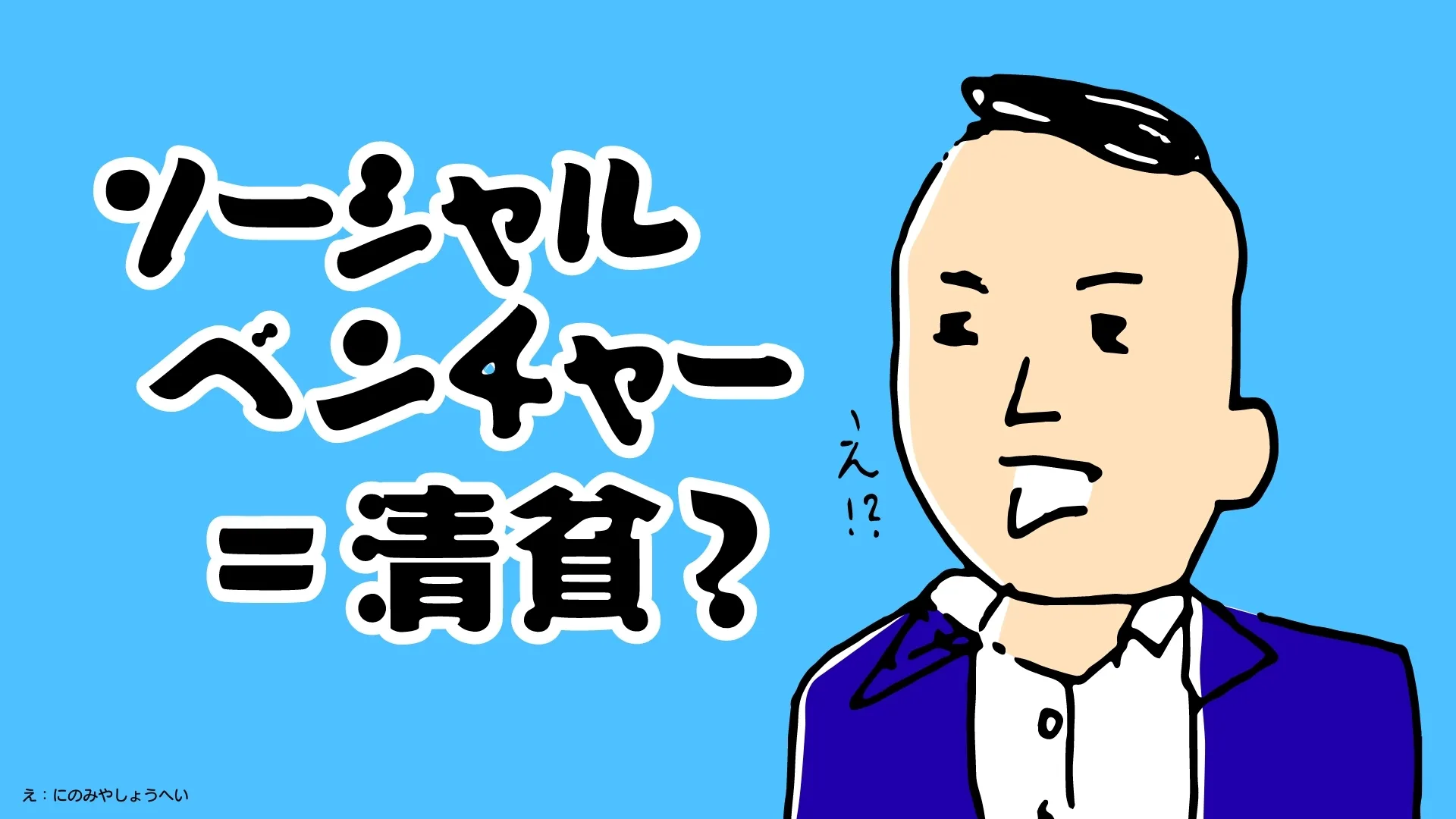「どうぶつの森事件」と組織カルチャー変革の決意
「むちゃくちゃ胸がざわざわしたんですよ」
「どうぶつの森」でつながる社員たちの姿に強い違和感を覚えた高橋社長は、組織カルチャーの見直しを決意。
創業期に起きたカルチャー設計の失敗と、それをどう乗り越えたのかを、自身の言葉で率直に語っています。
- 目次
- 「どうぶつの森事件」を振り返る
- 創業初期、組織づくりなんて何も知らなかった
- 「アットホームな職場」と違和感の蓄積
- 仲良し組織の完成と僕の不在
- 社員の会話に感じた“ざわざわ”
- 「どうぶつの森事件」からの決断と構造改革
- プライベートと仕事の線引き
- 会食=イベントとしての再評価
- 未来の組織への想いと今後
- 過去を語ることの意味
「どうぶつの森事件」を振り返る
さて、今回は「どうぶつの森事件」の話をしようと思ってます。
前にも話題に出したんですけど「あれ、改めて話そうよ」って言われたんで改めて話してみます。これ、僕の中ではかなり面白くて、象徴的なエピソードなんですよね。
これはミッションやパーパスの誕生の話じゃなくて、どっちかというと「組織カルチャーを僕が完全に間違えた」っていう話です。
創業初期、組織づくりなんて何も知らなかった
僕が会社を立ち上げたのは27歳のとき。大学時代から営業しかやってこなかった僕には、組織づくりの知識なんてまったくなかったんです。
創業2年目くらいで初めてアルバイトを採用したんですけど、応募してきたのが主婦っぽい人と気が強そうなギャルっぽい子で「まあ気が強い方がいいかな」って理由でギャルの子を採用しました。
彼女は会社の足りない部分をズバズバ指摘してくれて、それが全部正しかった。僕は「ごめん、それ作るわ」って、言われるがままに整備を進めていきました。社員が増えるたびに自然と「仲良くご飯行こう」みたいな空気になっていったのもこの頃です。
「アットホームな職場」と違和感の蓄積
「アットホームな職場です」ってよく見るじゃないですか。僕、あれ本当に苦手なんです。社員たちとご飯に行って、そこで話すのって仕事の話じゃなくて他愛もない話ばかり。
僕の中ではずっと「もっとでっかいことをやりたい」「もっと成長したい」っていう気持ちが渦巻いてたんです。でも「押し付けになるんじゃないか」という思いがあって口に出せませんでした。
さらに、創業メンバーって言えるような人もいなくて、知らない人を雇ってスタートしたから、価値観も方向性もバラバラ。
気づけば僕は“みんなに合わせる側”になってて、自分の中にズレが溜まっていきました。そのうち、ご飯会にも顔を出さなくなって、「なんか楽しくないな」と感じるようになったんです。孤独感もありましたが、それよりも「まぁいいか」と諦めるような気持ちのほうが強かった。この頃から、僕は他人と距離を取るようになっていったんだと思います。
仲良し組織の完成と僕の不在
結果として当初僕が狙いとしていた「みんな仲良い方がいいよね」っていう組織はできあがったんですよ。でも、その組織に僕がまったくハマってなかった。
当時の僕って、自分がどういう人間なのか、自分は何を大事にしてるのかっていう“自己分析”が全然できてなかったんです。「会社ってこうあるべき」みたいな外の情報ばっかり見て、それに当てはめて動いてた感じです。
ティール組織の本とか読んで「これが理想だ!」って思って、フラットな組織を目指したりもしてました。でも、今思えばあれって僕に全然フィットしてなかった。
やっぱり自分と向き合って、自分の価値観に合った組織を作るべきだったんですよね。
社員の会話に感じた“ざわざわ”
2020年、新卒一期生が入社したタイミングで、ちょうどコロナが始まりました。
出勤体制を続けていたある日、昼間は会社で一緒に働いて、夜は「どうぶつの森」でまた一緒に遊んでる──そんな社員たちの会話を耳にしたんです。それを聞いた瞬間、僕、めちゃくちゃ胸がざわざわしたんですよ。
昼も夜も会社の人と一緒って、完全にプライベートと仕事の境目がなくなってる。しかも、それが当たり前になっていく空気があって……。
家族的な組織って意見が言いにくいんですよね。気を使ってしまって本気でぶつかれない。人間関係ファーストになっちゃう。
そして何より嫌だったのが「会社が居場所になってしまう」ってことです。仲間に会いに会社に来る、みたいな。仕事をしに来てるんじゃなくてコミュニティに属してるだけになってる。これ、本当に僕の中では違和感しかなかった。
「どうぶつの森事件」からの決断と構造改革
どうぶつの森事件のあと、僕は覚悟を決めてコールセンター業務をアウトソーシングする決断をしました。表向きは「社員にもっと生産的な仕事をしてほしい」という理由でしたが、本音は「組織カルチャーを根本から変えたかった」。
仕事を外に出すことで、社員に「次は何をやるか?」という問いをぶつけました。でも全員が生産性の高い仕事に適応できたわけじゃなく、特に“どうぶつの森メンバー”はひととおり会社を離れていきました。
その後、数ヶ月から半年くらいかけてコールセンター業務を再構築したんですけど、今度はアルバイトさんとか派遣さんにお願いするようにしました。
そのときから「この仕事は社員がやるものじゃない」っていう意識が強くなったんです。むしろ社員にはもっとクリエイティブな仕事、生産性の高い仕事をしてほしいっていう。
で、今では逆に「この仕事は超重要だから社員がやる」っていうスタンスになってるんですけど、それは組織が大きくなって、役割分担が明確になったからなんですよね。
プライベートと仕事の線引き
あの事件をきっかけに、僕の中で「仕事とプライベートの線引き」はめちゃくちゃ大事だなって思うようになりました。
当時ははっきり言ってました。「社員同士でプライベートで仲良くするのは推奨しません」って。特に派遣さんとの関係とかはトラブルの元にもなるし、絶対にやめてくれって伝えてました。
もちろん、社員同士で仲が良いのは悪いことじゃない。でも、それが仕事に影響するなら、それは違うと思うんです。
僕が伝えたかったのは、「仕事に集中できる環境を作ろうぜ」ってことなんですよね。
会食=イベントとしての再評価
最近は少し考えが変わってきてて「社員との食事会」もちゃんと目的があれば意味があるなって思ってます。
当時は「なんとなく仲良くなろう」とか「友達感覚でいよう」みたいなノリでやってたから、むしろ害になってた。でも今だったら目的が2つあるんです。
1つ目は社員のリアルな声を聞くこと。現場の人たちがどう感じてるのか、会社に対してどんな不満や期待があるのか、ちゃんと知りたいって思ってます。
2つ目は文化づくりの一環。お祭り的な雰囲気とか、年に1回の表彰式みたいなイベントも、会社にとっては大事な儀式だなと思うようになってきました。
未来の組織への想いと今後
今はもう社員同士のプライベートにはほとんど口出ししません。基本的に自由。でも「仕事に支障が出るような関係性はダメだよ」っていうのは今も伝えてます。
あの頃と比べて僕自身の考え方も、会社のステージも変わってきたんですよね。
今は「仕事を通じて信頼を築こう」とか「社員同士の相互理解は別に飲み会じゃなくてもできるよね」っていう方にシフトしてます。
実際、動画での自己紹介とか、1on1のコミュニケーションとか、いろんな方法で相互理解は深まるし、そこにちゃんと時間を使うことが大事だなって思ってます。
過去を語ることの意味
今回の「どうぶつの森事件」の話って、僕の中ではけっこう勇気がいる話だったんですよ。
正直「ひどい社長だな」って思われるかもしれないし、昔の自分を振り返るのって、痛みもある。でも、これをオブラートに包んじゃったら意味がないなって思ってて。
だから当時の気持ちも含めて、ちゃんと話しました。
あの時期があったからこそ今のカルチャーができてきたし、あの判断をしてよかったって、今では思えるようになってます。
会社は今、僕が理想とする「ミッションドリブンな組織」に近づいてきていると思います。もちろんまだまだ課題もあるけど、あの頃の経験がすべての土台になってるのは間違いないです。
話し手
高橋 翼
株式会社アーラリンク代表取締役社長
2011年早稲田大学社会科学部卒業。通信事業の将来性と貧困救済の必要性を感じ2013年にアーラリンクを創業。