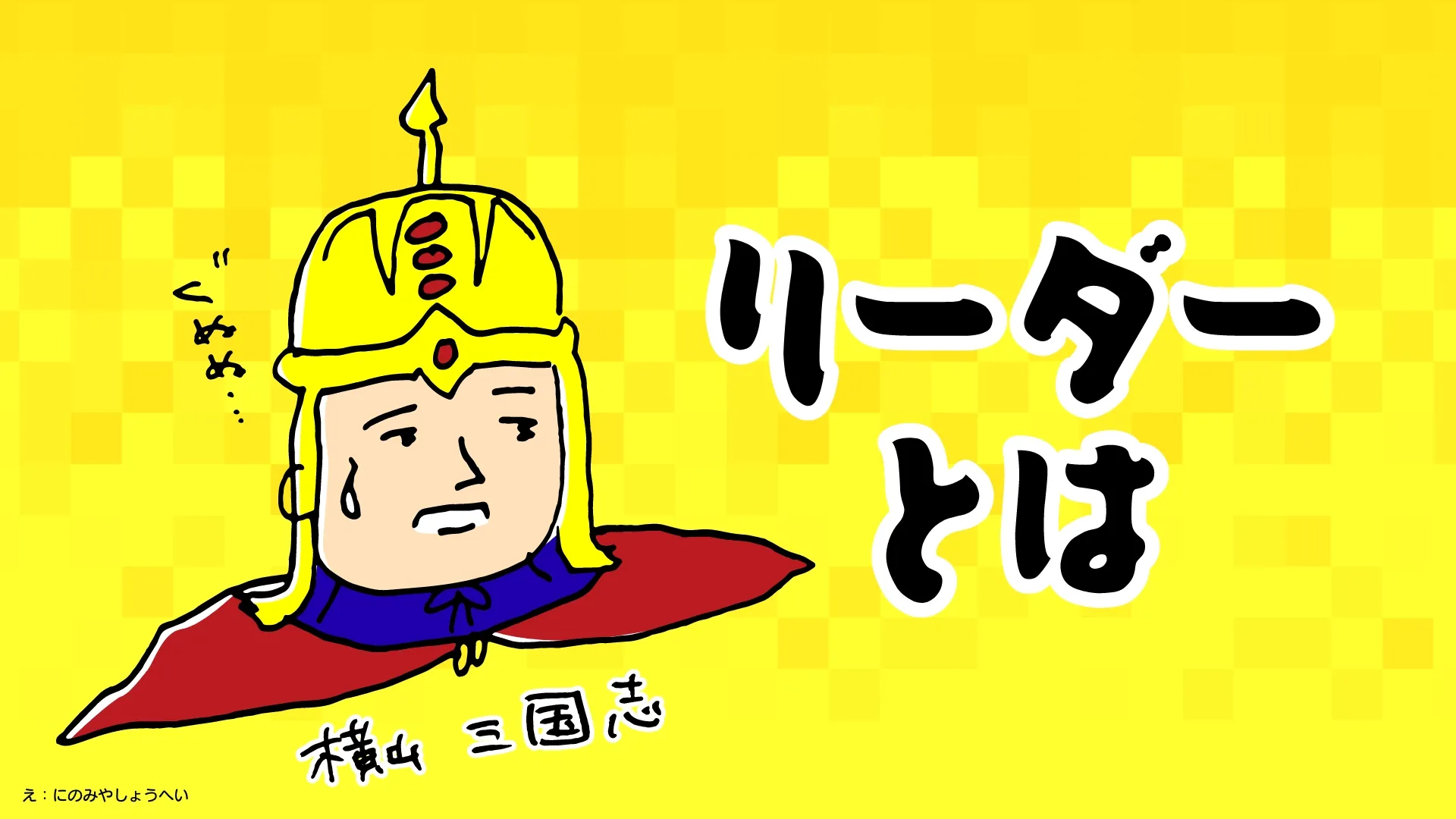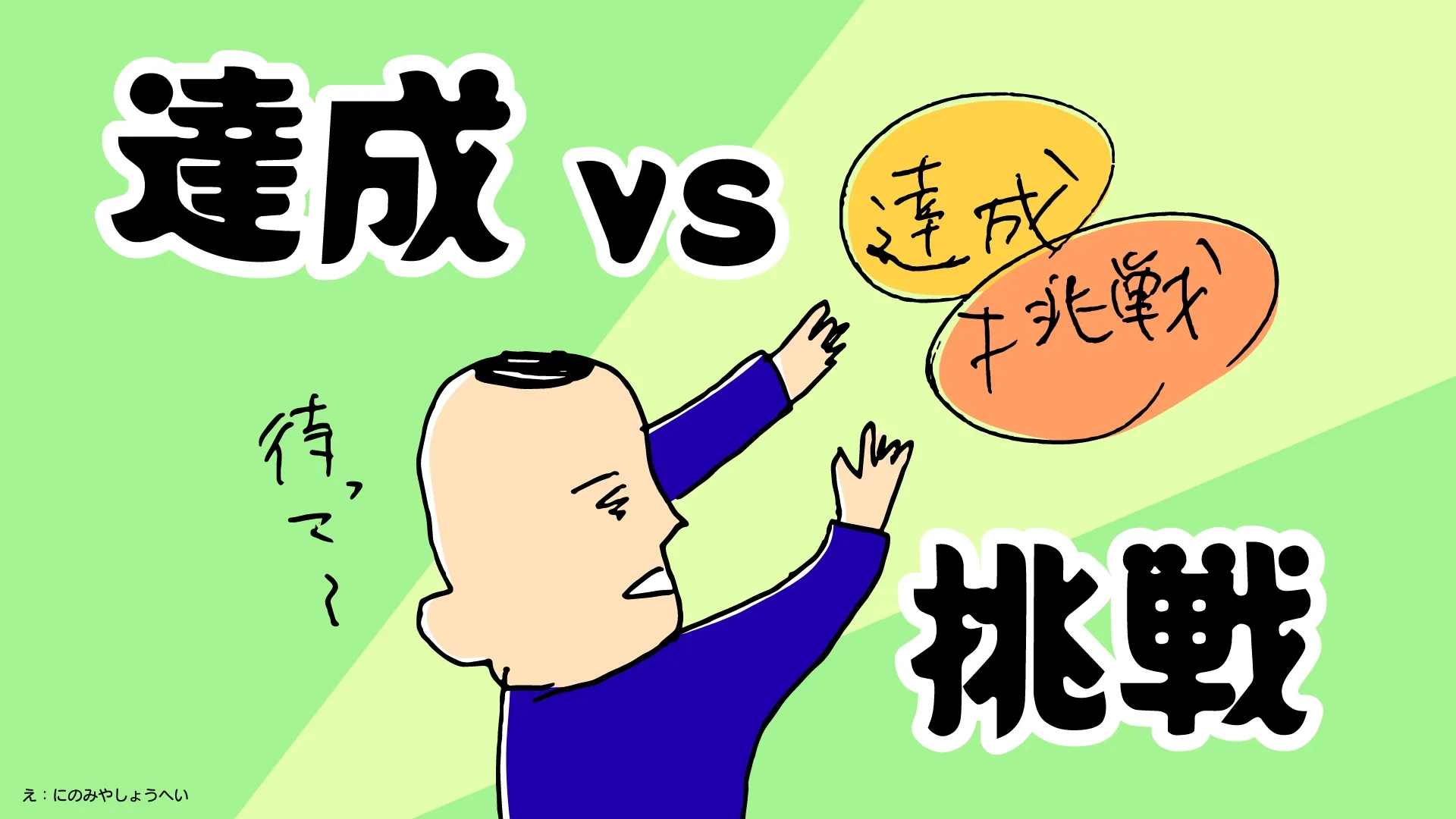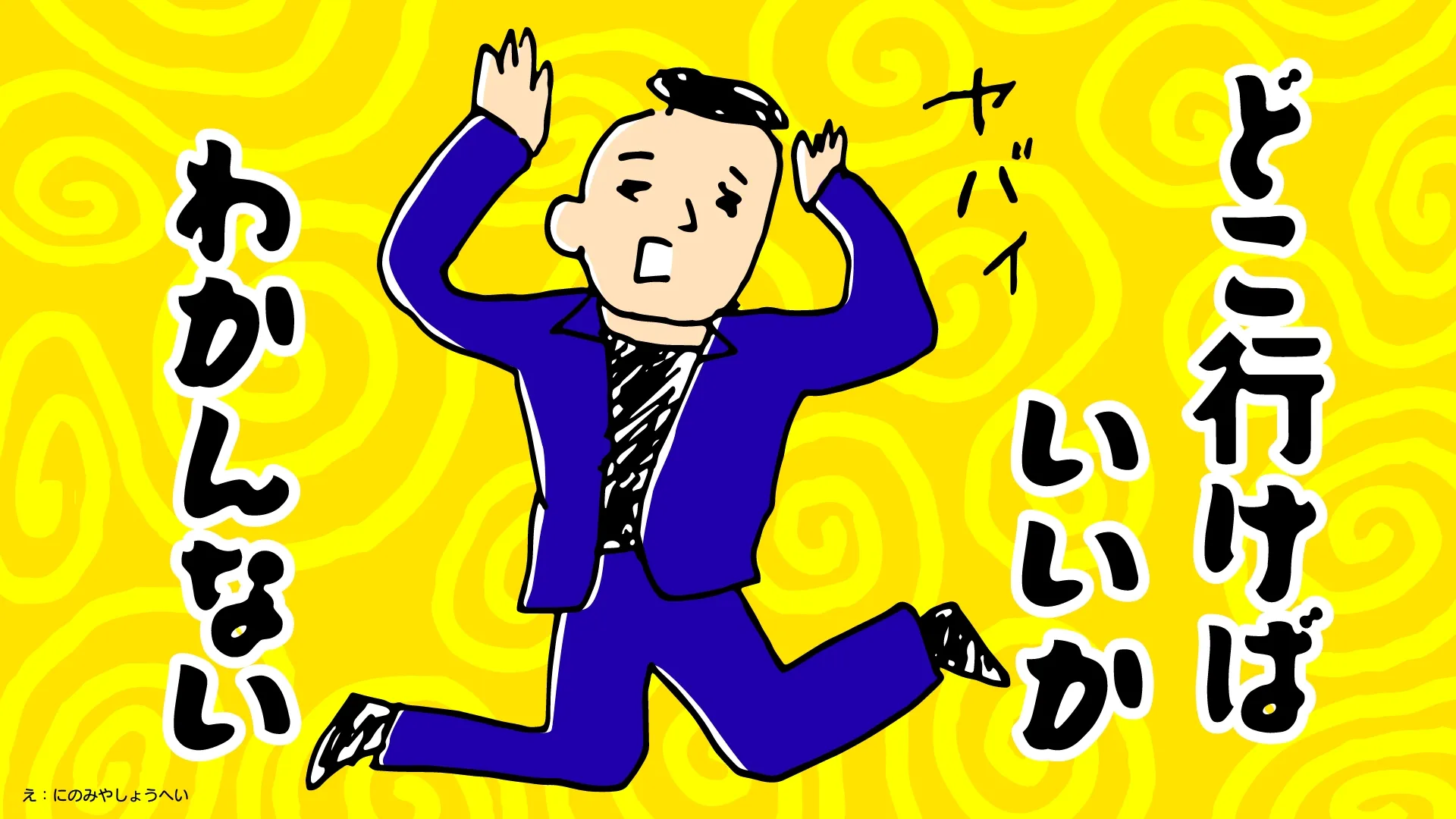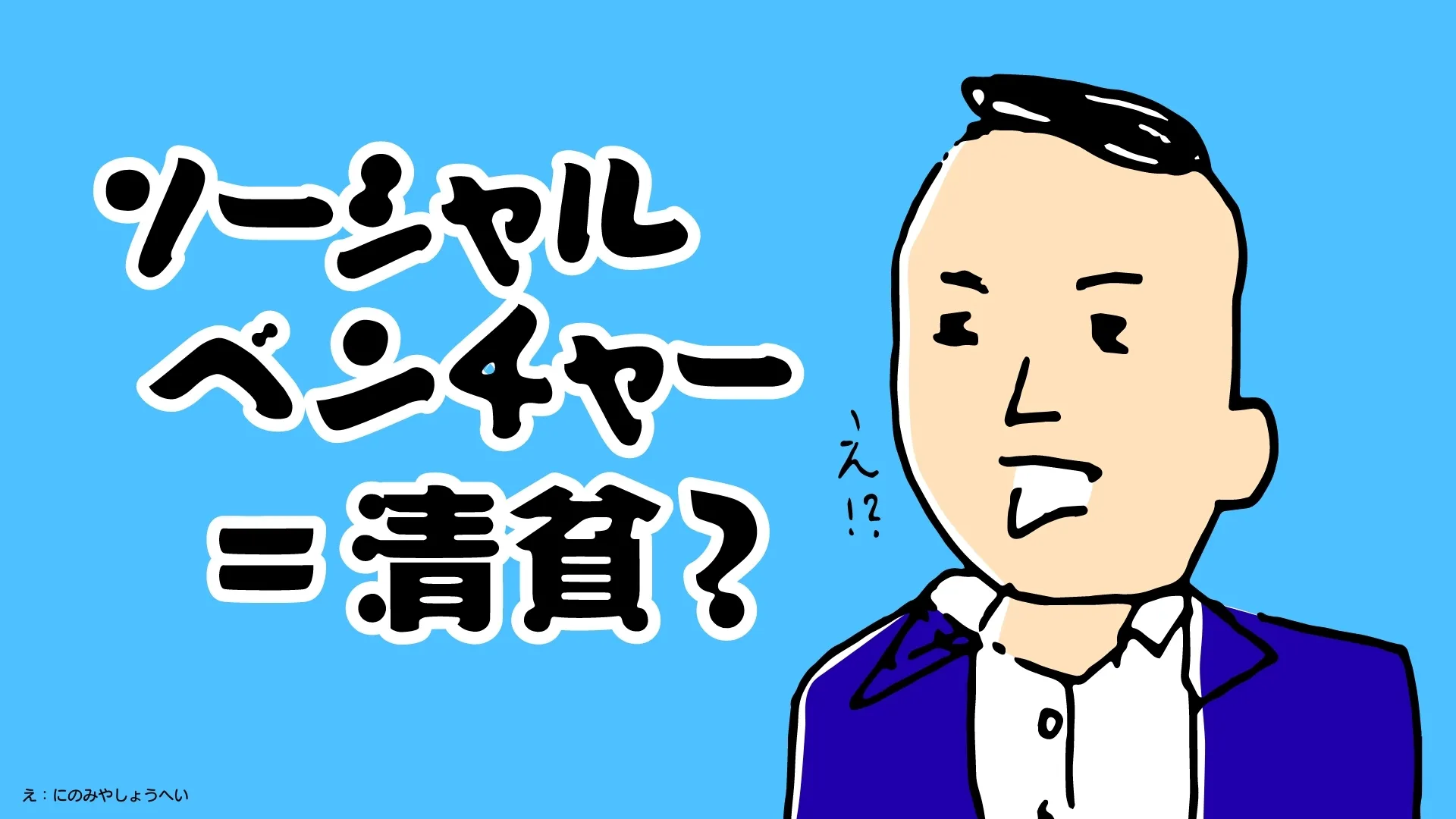「器の大きさが組織を決める」三国志に学ぶ“受け入れるリーダー像”
「失敗を受け入れる器を大きくしていかないと組織は大きくならない」
横山光輝『三国志』の中に描かれる、我慢・信頼・覚悟でつくられるリーダー像。
その姿に、高橋さんが経営する組織のフェーズ(30人→50人→100人)を重ねながら、組織づくりに必要な“器の大きさ”について語ります。
- 目次
- 今さらハマった横山光輝の『三国志』
- 「我慢」と「器」に学ぶリーダーシップ
- 組織フェーズとリーダー像の関係性
- リーダー育成の難しさと「欲の強さ」
- チームに「理想を語る場」を設けるべき
- 自由な裁量とリーダーの育成
- リーダーを輩出できる会社が生き残る
- 再現性あるリーダー育成への挑戦
- 結論はまだ出ていない。でも、考え続けたい
今さらハマった横山光輝の『三国志』
最近、改めてハマっているものがあります。それは、横山光輝さんの漫画『三国志』です。経営者の間では昔から「リーダーシップの勉強になるから読んでおいた方がいい」とよく勧められていた作品ですが、全巻セットを購入して2年ほど本棚に眠らせていました。
そんな『三国志』をようやく読み始めてみたところ、これが非常に面白い。全70巻あるうち、今はまだ15巻あたりですが「ああ、みんなが言っていた“学び”ってこれか」と深く納得しながら読み進めています。
「我慢」と「器」に学ぶリーダーシップ
『三国志』に登場するリーダーたちの姿には、非常に多くの学びがあります。彼らは総じて“我慢する力”が強いんです。
たとえば、戦の現場を任された部下が成果を上げられず、敵に敗れて帰ってくるような場面。普通なら「見せしめに首を斬れ」と処罰する展開がありそうなところですが、彼らは「それでは誰も武将をやりたがらなくなる。だからここは我慢してほしい」と抑える。
また、酒癖の悪い武将が何度も「飲むな」と注意されたにもかかわらず再び酒を飲み、失敗してしまうというエピソードもあります。本人は「自分は失敗したから死ぬ」とまで言い出しますが、そこを「俺たちは兄弟としてここまで来たんだ。一緒に死ぬと誓っただろ」と思い留まらせる。そういった人間味にあふれるシーンが随所に描かれています。
これは僕にとって非常に大きな学びです。失敗を受け止める器や、部下を信じて我慢する姿勢。そうした在り方に、本当のリーダーシップがあると感じさせられました。
組織フェーズとリーダー像の関係性
現在、僕が経営しているアーラリンクも30人から50人という組織フェーズを超え、次は100人の壁に挑もうとしている段階にあります。
こうした規模になると、単なる1対1の関係性だけでなく「そのやりとりを誰かが見ている」という“公開されたリーダーシップ”の感覚が必要になってきます。
たとえば、部下が失敗したときにリーダーがそれをどう受け止めるか。その姿勢は周囲に伝わり、組織全体の信頼構築にもつながる。だからこそ、リーダーとしての器の大きさがますます重要になってくると実感しています。
リーダー育成の難しさと「欲の強さ」
最近、社員たちのリーダーシップをどう育てていくかについても悩んでいます。「いいリーダーを輩出するには、何が必要なのか?」を改めて学び直しているところです。
その中で、森岡毅さんの著書『誰もが人を動かせる!』を読みました。とても印象的だったのが「欲の強さがリーダーのデフォルト条件である」という言葉です。
なるほどと思いました。一見、最近の若い人たちは欲が薄いように見えるかもしれません。でも実際には、欲の“表れ方”や“満たし方”が変わっただけなんですよね。
かつてのように「車がほしい」「時計がほしい」といった形ではなく、今はスマホの中やSNSで満たしている。つまり、欲が見えにくくなっているだけなんです。
チームに「理想を語る場」を設けるべき
たとえば、ある社員がリーダーになったとして「明日からSV(スーパーバイザー)です」と肩書きを与えられたとします。
でもその人に「どんなチームを作りたいか?」「どんな風にメンバーと向き合いたいか?」といったビジョンや理想を語る機会がないと、役職だけで中身が伴わない“管理者”にとどまってしまう可能性がある。
本来、リーダーは「自分はこうしたい」という感情や欲を言葉にして、それに共鳴した人たちが自然とついてくる存在だと思うんです。
だからこそ、そうした“理想を語る場”や“想いを引き出す仕組み”を会社として設計できているか。現時点では、僕自身「全然できていないな」と痛感しています。
自由な裁量とリーダーの育成
リーダー育成において、もう一つ課題だと感じているのが「権限移譲」の難しさです。僕は基本的にできる限り任せるスタンスでいたいと思っていますが、実際にはついつい口を出してしまっていることもあります。
逆に、完全に放任してしまうこともできなくはないんですが、それはそれでリスクが高い。任せきりにした結果、失敗して自信を失ってしまう人も出てきてしまう。
だからこそ任せるにも段階が必要で、リーダーとしてのステップをちゃんと踏めるような設計が必要だと思っています。
僕自身は一人で起業して、一人ずつ仲間が増えていく中で自然とリーダーシップを学んできました。でも、そういった“自然な環境”があるわけではない今の会社においては、もっと構造的・意図的に設計していかないといけないと感じています。
リーダーを輩出できる会社が生き残る
結局のところ、これからの時代において強い会社とは「リーダーを輩出できる会社」ではないでしょうか。
逆に言えば、それができない会社は遅かれ早かれ淘汰されてしまうのではないかと強く思っています。
ただし、それはとても難しいことです。単に権限を渡せばリーダーが育つわけではありませんし「自由にやっていいよ」と言われたことで、かえって混乱してしまう人も少なくありません。
自由というのは一見魅力的に見えるかもしれませんが、実際にはものすごく大変なものです。会社員として働いていると「自分はこれだけの給料だから、これだけやっておけばいい」という発想になりがちです。
でも自由を与えられると、自分で意思決定して自分で構造を設計していかなければならない。これは想像以上にハードなことです。
再現性あるリーダー育成への挑戦
僕が普段チームを引っ張るときは、強い意志を持って前に立ち、それに共鳴した仲間がついてきてくれる、そんなスタイルでやってきました。でもそれは“相性が合っていた”だけかもしれないし、誰にでも真似できるやり方ではありません。
「真似したいけど無理」「あのやり方は自分には合わない」と思う人がいて当然です。だからこそ、会社として“再現性のあるリーダー育成”を考える必要があります。一人ひとりが自分らしいリーダーシップを見つけられる環境を整えていくことが、僕のいま最も注力しているテーマです。
リーダー育成を“仕組み化”するのは簡単ではありません。「それって社長だからできるんでしょ?」という声もあるように、立場による見え方の違いもあるでしょう。だからこそ、現場のフェーズや役割に合わせて「どんなリーダーを求めるのか」「そこにどう導くのか」を丁寧に設計する必要があると感じています。
結論はまだ出ていない。でも、考え続けたい
正直なところ、まだこれといった明確な結論は出ていません。でも、間違いなく言えるのは「リーダーが育つ会社は強い」ということです。
権限を渡すこと、それは信頼の表現でもあります。その信頼が本物であるためには、単に任せるだけでなく、育てる仕組みも整えなければならない。
僕自身、今はその構造を模索している段階ですが、これからも試行錯誤を繰り返しながら、より良いチーム、より良い組織づくりに向き合っていきたいと考えています。
話し手
高橋 翼
株式会社アーラリンク代表取締役社長
2011年早稲田大学社会科学部卒業。通信事業の将来性と貧困救済の必要性を感じ2013年にアーラリンクを創業。